経理業務を効率化する5つの方法|成功事例とポイント・注意点を解説
-
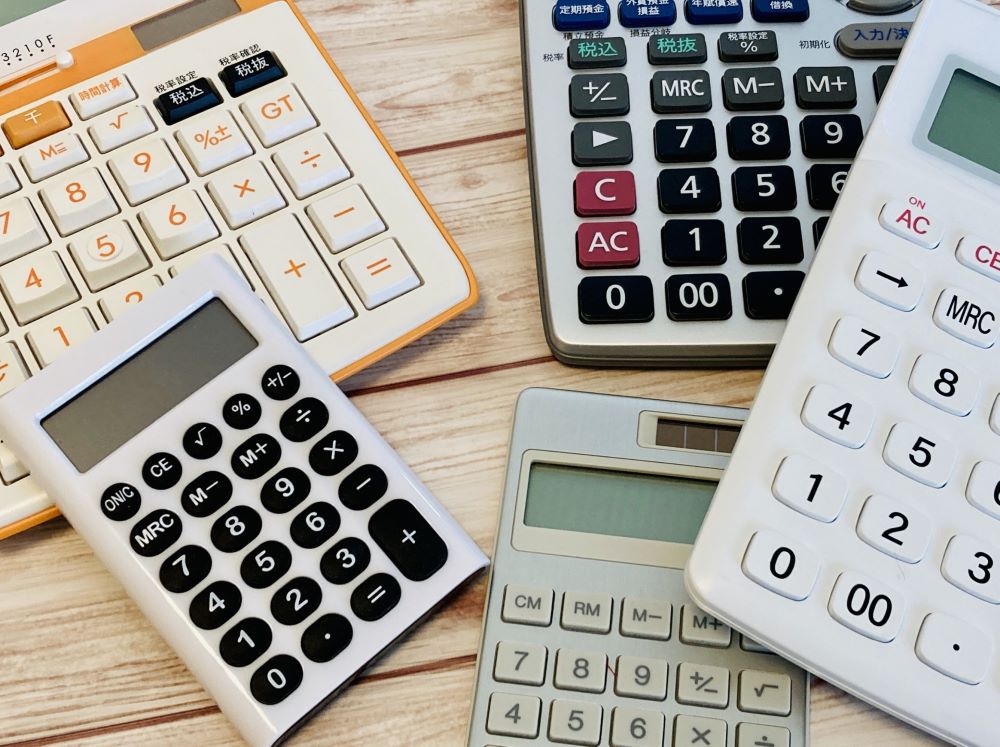
-
人手不足や業務属人化、法改正への対応も加わり、経理業務の負担が増大している企業が多い現代では、経理業務の効率化を図りたいと考える企業が増えています。
本記事では経理業務の効率化における課題とポイント、具体的な方法と注意点を解説します。
経理業務効率化の成功事例も紹介しますので、自社の課題解決の参考にしてください。
この記事でわかること
- 経理業務を効率化する方法とポイント・注意点
- 経理業務を効率化するステップと成功事例
- 経理業務をアウトソーシングするならFammアシスタントオンラインがおすすめ
\ 月額¥60,000~利用できる /
資料「Fammアシスタントオンラインサービス」
を無料ダウンロード目次
経理業務の基本
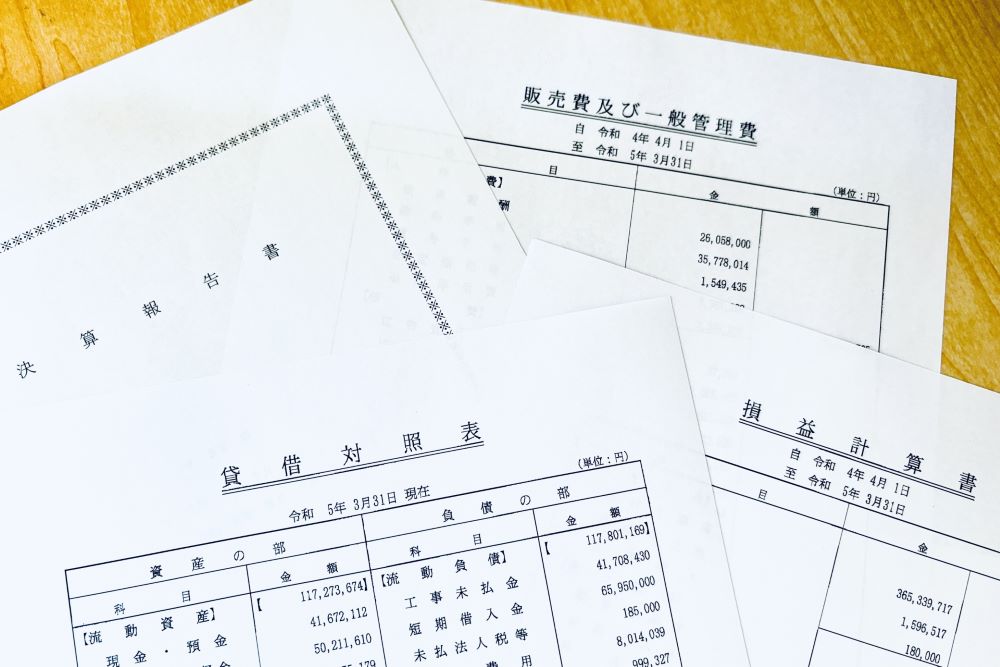
企業における経理は、企業のお金の流れや取引の詳細を記録・管理すると同時に、企業の財務状況を把握し、経営陣に改善提案を行う職務も担うセクションです。
具体的な業務は、毎日行う「日次業務」、月間サイクルで行う「月次業務」、1年に1度行う「年次業務」に分類されます。
業務頻度
具体的な業務内容
日次業務
- 現金出納管理
- 経費精算
- 売上集計
- 伝票記帳・整理
- 売掛金や買掛金の管理 など
月次業務
- 在庫管理
- 給与計算と社会保険料の計算
- 領収書・請求書の発行
- 月次決算書の作成
- 予算実績管理 など
年次業務
- 決算整理
- 年次決算書作成
- 税務申告
- 賞与計算・振込
- 社会保険の算定基礎届提出
- 労働保険の更新
- 中間税務申告
- 賞与計算・振込
- 年末調整
- 給与支払報告書・法定調書の提出
- 償却資産税申告書提出
- 実地棚卸 など
経理担当者の扱う業務は、社内の経費精算や外部との取引会計まで広範に及びます。企業の財務状況データを資料にまとめ、経営陣や社外のステークホルダーに経営状況が一目でわかるよう整備するのも経理担当の役割です。
経理のデータにもとづき経営陣が意思決定を下すため、経理は企業経営における中核的なポジションといえます。
効率化すべき経理業務の3つの課題

効率化が必要とされる経理業務の主な課題は以下の3つです。
- 紙ベースの帳票が多い
- 業務の専門性が高く属人化しやすい
- 法改正への対応が必要
それぞれの課題について詳しく解説します。
紙ベースの帳票が多い
経理業務には紙ベースの帳票が多く非効率の原因となっています。
近年は社内の多くの作業で電子化が進んでいるものの、以下の経理業務は現在でも紙ベースの処理が少なくありません。
- 請求書発行業務
- 請求書受領および支払い業務
- 受注・出荷・売上の集計業務 など
紙ベースの処理・管理には確認業務やExcelへの入力業務、Excelからのデータ抽出、帳票への転記・印刷など、工数とコストが発生します。また、紙ベースの処理は手作業のため、ヒューマンエラーの発生確率が高まることも経理業務の問題点です。
業務の専門性が高く属人化しやすい
経理業務には専門性の高い知識やスキルが必要となるため、特定の担当者に業務が集約され属人化しやすいことも経理業務の課題です。
決算整理仕訳などの年次業務がある経理は習得に時間がかかり、一通りの業務を覚えるには少なくとも3~5年が必要といわれています。そのため、誰かが業務を覚える間に熟練者のみに業務が偏ると、他の社員と共有することが難しくなります。
属人化が起こると業務内容がブラックボックス化し、担当者の不在時に代替できる者がおらず、業務が滞ってしまう恐れもあるでしょう。
法改正への対応が必要
税法や会計基準の改正があるたびに、知識の刷新と業務フローの変更を強いられることも経理業務特有の課題です。
2022年には電子帳簿保存法が改正され、領収書や請求書などの情報を電子取引化する必要が生じました。
また、2023年10月からのインボイス制度への対応も迫られ、経理業務はいっそう煩雑になっています。経理担当者は既存の業務を遂行しながら、追加で新しいルールに準拠するための業務に対応しなければなりません。
度重なる制度変更へ的確・スムーズに対応するためにも、経理業務の効率化は必須といえます。
経理業務効率化で得られるメリット

経理業務の効率化により、経理担当者と自社に得られるメリットは以下の通りです。
- 業務コストの削減につながる
- ヒューマンエラーを削減できる
- 経理担当者がコア業務に集中できる
- 経営判断のスピード化につながる
それぞれ見ていきましょう。
業務コストの削減につながる
経理業務が効率化されると、資材・人材の両面でコスト削減につながります。
紙書類を電子化すれば、従来の用紙代や印刷代が不要になります。書類のやり取りもWeb上で完結するため、郵送やメール便の費用もかかりません。
さらに業務の工数を削減すれば残業や休日出勤も減らすことができ、人件費の削減につながります。システムの導入によりテレワークが可能になれば、通勤手当の削減も可能です。
ヒューマンエラーを削減できる
効率的な業務体制が整備されると、経理担当者が無理なく業務を進められ、ヒューマンエラーの減少にもつながります。
経理業務にITツールやシステムを導入することで、手作業の仕事を減らす代わりに、システムによる正確なデータ処理へ移行が可能です。また業務自動化により担当者の負担が減少すれば、作業中に集中力を持続できるようになり、ミスの軽減が期待できます。
経理担当者がコア業務に集中できる
経理の業務が効率化されれば、経理担当者がコア業務に集中が可能です。
経理業務は以下のコア業務とノンコア業務に分かれます。
- コア業務:業績管理、予算管理、決算業務
- ノンコア業務:立替経費精算、現金出納管理、請求書発送
作業的な要素の多いノンコア業務は、ツールやシステムによる自動化がしやすい業務です。帳簿の二重チェックなど、手間のかかる作業がなくなるだけでも大幅な業務時短につながります。
一方で、経営判断の元となり将来の利益拡大につながる企業業績関連の業務は、専門的な判断が必要となるため、自動化・効率化が難しい業務領域です。
ノンコア業務だけでも効率化できれば、経理担当者は経営に貢献する業務に専念できます。
経営判断のスピード化につながる
経理業務の効率化により、経理が企業の業績に関わるコア業務に集中できれば、経営判断のスピード化にもつながります。
近年は社会のDX化により事業展開のスピード化が求められており、迅速な経営判断が不可欠です。
業務の自動化・効率化が進めば日常の取引業務処理が円滑化され、財務分析の処理速度の高速化も可能です。経営陣がより精度の高い判断を下せるようになり、事業運営のスピードアップにつながります。
経理業務効率化のデメリット
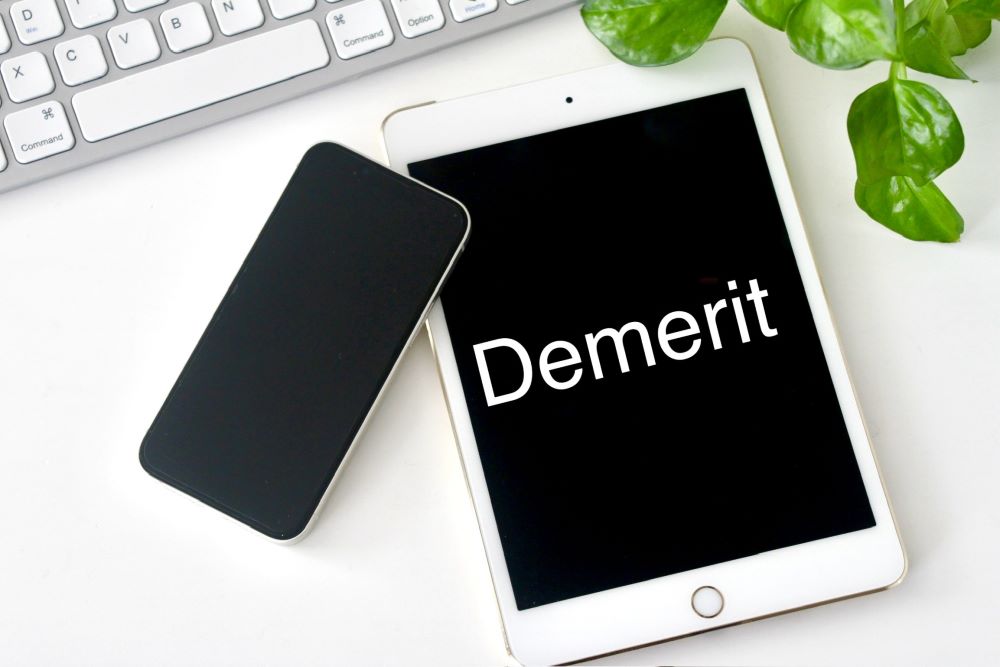
経理業務の効率化にはさまざまなメリットがある一方で、デメリットもあります。
- 初期費用が発生する
- 経理担当者にITリテラシーが求められる
業務効率化の施策を考えるうえでは、メリットとデメリット両面の考慮が必要です。
初期費用が発生する
新たなシステムやITツールの導入には初期費用がかかるサービスもあります。会計システムを導入する場合の初期費用は以下の通りです。
導入手法
特徴
初期費用の相場
パッケージソフトウェア
- 比較的安価で導入が容易
- 機能が限定されカスタマイズが困難
20,000〜100,000円程度
クラウド型(SaaS)
- 初期費用がほとんどかからず導入が容易
- 長期利用は割高になる場合がある
導入料金は無料のサービスが多い
(月額料金10,000〜50,000円程度が必要)
自社開発(フルスクラッチ)
- 自社向けにカスタマイズしやすい
- 構築費用が高額
- 開発に期間を要する
300万〜数千万円
企業によってはシステム以外に、PCなどの機器導入が必要なケースもあります。
高額な初期費用は業務効率化の施策を検討する際にハードルが高く感じるかもしれません。しかし将来的に初期費用を回収でき、かつ担当者や顧客の満足度向上につながるのであれば投資する価値はあるでしょう。
初期費用の投資は中長期的視野で判断することが大切です。
経理担当者にITリテラシーが求められる
ITツールを導入する場合、経理担当者のITリテラシーが高くなければ使いこなせない可能性があります。
特に長年紙ベースの処理をしてきた従業員は、ツールやPC作業の習得に時間がかかります。さらにリモートワークに対応できるシステムを導入した際には、担当者にネットワークリテラシーがなければ情報漏洩リスクが生じます。
しかし、担当者が通常業務と並行して、ITリテラシーを習得することは容易ではありません。IT教育を行う場合は、担当者の負担になりすぎないよう配慮が必要です。
経理業務を効率化する際に押さえるべきポイント

経理業務の効率化を進める際に押さえておくべきポイントは、以下の通りです。
- 担当者の些細なミスには柔軟に対応する
- 事前に業務担当者の理解を得ておく
- 経理業務効率化を全社的な取り組みとして行う
- 経理担当者のITリテラシーを向上させる
改善施策の成否に関わるポイントのため、確実に押さえておきましょう。
担当者の些細なミスには柔軟に対応する
経理業務のスピード化を図る際には、担当者の些細なミスに対して柔軟な対応が求められます。
経理の業務は、正確性が求められるため、ミスを容認することはできません。しかし、細かなミスを指摘しすぎると、プレッシャーによる余計な確認作業が増え、仕事が遅くなる可能性があります。
即刻修正しないと後の業務に支障が出る致命的なミスでない限り、容認することも必要です。
事前に業務担当者の理解を得ておく
経理業務の効率化にITツールやアウトソーシングを導入する場合、事前に担当者へ説明し、理解を得ておくことが大切です。
業務効率化の過程では、従来の工程やフローが大きく変わります。そのため事前に説明がなくツールや外部人材を採用すると、担当者が戸惑いや反発を感じてしまう可能性があります。
実務を担う担当者には、業務効率化のために省いた工程やツールの操作法、外注先との業務の割り振りなどを事前に伝えておきましょう。
経理業務効率化を全社的な取り組みとして行う
経理業務の効率化を全社的な取り組みと捉え、他部署を巻き込むことも大切です。
例えば、 経理で集計する受注や出荷、売上などの報告については、営業部門との連携が必要となり、経理部門だけでDXの推進を図るのは難しいでしょう。
また、経理は経費精算を通じてすべての部門に関与します。各現場で経費精算書を正しく作成してもらうなど、全社を巻き込むことで大幅な効率化が可能です。
経費精算をシステム化すれば、各現場の請求データをそのまま経理で処理できるので、ミスも減り大幅な効率アップを図れます。
経理担当者のITリテラシーを向上させる
先述したように、経理業務の効率化にITツールを導入する場合は、経理担当者に一定のITリテラシーの習得が欠かせません。
経理担当者が習得すべきITリテラシーは以下の3つです。
- 情報基礎リテラシー:情報の正誤を見極める能力
- コンピューターリテラシー:デバイス操作のスキルや知識
- ネットワークリテラシー:ネットワークやセキュリティの理解とインターネット上のモラル
経理業務のシステム化に必要な知識を学ぶには、資格試験や専門家による講習の受講が効果的です 。
- ITパスポートや情報セキュリティマネジメント試験を受検させる
- ITの社内研修や社外講座を受講させる
将来的には一部の経理担当者にシステムのメンテナンスや管理、システムエンジニアとの連携といった業務を担ってもらうことが理想です。これにより、経理業務のさらなる効率化と高度化が期待できます。
経理業務を効率化する具体的な方法

ここからは経理業務を効率化する具体的な方法を解説します。
- ペーパーレス化・キャッシュレス化
- 帳票関係のフォーマットの統一
- 会計ソフトによるシステム化
- アウトソーシングの活用
- コンサルティングの導入
自社の課題を把握し、解決につながる方法を選択しましょう。
ペーパーレス化・キャッシュレス化
経理業務をペーパーレス化・キャッシュレス化することで、大幅な業務効率化が可能です。
紙の帳票は取り出しや収納、管理に手間がかかる上 、紛失のリスクも高まります。改正電子帳簿保存法により電子取引のデータ保存も義務化されたため、書類はクラウドシステムやExcelで電子化して正しく保管しなければなりません。
また小口現金の出納も煩雑な業務であり、企業によっては複数の担当者が処理するケースもあります。さらに横領などの不正リスクもあるため、経費精算をシステム化し、キャッシュレス化する方が安全かつ効率的です。
帳票関係のフォーマットの統一
社内の帳票のフォーマットが統一されれば、経理業務の効率化につながります。
部署ごとに異なるフォーマットの見積書や請求書を使用すると、経理が必要な情報を探す際に、時間がかかるため非効率的です。
社内でフォーマットを統一できれば、経費精算をシステム化できるため処理がスピードアップします。まず現在、各部署で使われているフォーマットを確認して統一が可能かどうかを検討しましょう。
会計ソフトによるシステム化
会計ソフトの導入も経理業務効率化に効果を発揮します。
会計ソフトを使えば帳簿の作成から転記まで自動で行えるため、作業工数を大幅に削減できます。さらに計算ミスもなくなるので、二重チェックや帳票の作り直しの必要もありません。
クラウド型(Saas型)の会計ソフトであれば導入コストがほとんどかからず、月額費用が安価なサービスを選ぶことも可能です。さらにクラウド型は法改正の様式変更にも自動的に対応してくれるため、法改正のたびに自社でフォーマット変更する必要もなくなります。
アウトソーシングの活用
経理業務の効率化にはアウトソーシングの活用も有効です。
経理業務に人材を採用した場合、給与や賞与、社会保険料などの継続的なコストがかかります。しかし決算期などの繁忙期のみアウトソーシングを利用すれば、委託した業務の費用のみで済み、人件費の削減が可能です。
さらにアウトソーシングサービスでは、一般に即戦力の人材をアサインしてくれるため、研修期間を設けずに業務を任せられます。ITリテラシーの高い人材に業務を委託すれば、ITツールやシステムの導入もスムーズに進められるでしょう。
法改正対応など最新の業務に柔軟に対応できることも、アウトソーシングを活用するメリットです。
コンサルティングの導入
自社で効率化する業務の切り分けや優先順位付けが難しい場合には、業務改善コンサルタントに依頼するのも一つの方法です。
業務改善コンサルタントとは、企業の業務フローや業務プロセスの改善を以下の方法でサポートしてくれるサービスです。
- 業務プロセスの可視化と問題点の抽出
- 課題解決のための改善案提案
- ITツールなどの導入サポート
- 改善施策の効果測定
業務改善コンサルタントには、システム化、アウトソーシング導入のどちらが自社に適しているかなど、業務改善の具体的な方法を相談できます。ITツールやアウトソーシングのサービス会社がコンサルティングを提供しているケースも多いので、活用するのもおすすめです。
経理業務を効率化する際の注意点

経理業務の効率化でシステムやアウトソーシングを導入する際に、手順や方法を誤ってしまうと現場の混乱を招きかねません。
施策実行時の注意点を以下に分けて解説します。
- システム化する場合
- アウトソーシングを活用する場合
システム化する場合
経理業務をシステム化する場合の注意点は以下の通りです。
- 既存システムとの連携が可能か
- 自社の業務フローに合わせてカスタマイズ可能か
- 担当者の使い勝手が良いか
- セキュリティ対策は万全か
既存システムとの連携が可能か
導入を検討しているシステムが、自社の基幹システムや他の既存ツール・システムと連携が可能かどうか、事前に確認が必要です。
連携できなければ、新システムへのデータ移行が困難になったり、既存ツールを使用できなくなる可能性があります。システムを長く運用するためにも、連携の可否を確認しておきましょう。
自社の業務フローに合わせてカスタマイズ可能か
システムやツールの導入時には、自社の用途や目的に合わせて、機能の追加が可能かどうかを確認することも大切です。
パッケージツールを導入する場合、自社の業務フローに最適化できない可能性もあります。料金だけで選ばず、自社にカスタマイズが必要かどうか、必要な場合はシステムの拡張性についても検討しましょう。
担当者の使い勝手が良いか
業務効率化のためのツールは機能の豊富さより、現場での使い勝手を優先する必要があります。
どれだけ高機能でも経理担当者がツールを使いこなせなければ意味がありません。無料お試し期間などを利用して現場に使い勝手をヒアリングし、使いやすいツールを選びましょう。
セキュリティ対策は万全か
経理業務では、取引記録や社内の重要機密などを扱うケースが少なくありません。そのため、ツールのデータセンター側のセキュリティ体制と、ツールのアクセス制限設定について事前にチェックしておきましょう。
ただしセキュリティを優先した場合、動作スピードや利便性が劣ることもあります。自社で扱うデータの量と性質を考慮し、適切なセキュリティレベルを判断することも大切です。
アウトソーシングを活用する場合
続いて、経理業務の効率化にアウトソーシングを活用する場合の注意点を解説します。
- 必要な業務に対応しているか
- 業務量の変動に対応できるか
- 円滑なコミュニケーションが可能か
- 信頼できる導入実績があるか
必要な業務に対応しているか
アウトソーシング会社により対応する業務が異なるため、自社で委託したい業務に対応しているかどうか、事前に確認が必要です。
また、外注コストを抑えたい場合には、業務単位で切り分けて委託できるかチェックをしましょう。サービス選びの前に委託したい業務を洗い出しておき、個別に対応可否を確認することをおすすめします。
業務量の変動に対応できるか
業務量の変動に対応できるかどうかも、アウトソーシング会社選びの重要なポイントです。
経理業務は年間を通じて業務量が大きく変動する特徴があります。業務量の変動に応じた柔軟なリソース提供を受けられなければ、閑散期に人件費が割高になり、外部人材を活用する利点を活かせません。
アウトソーシング会社を選ぶ際には、業務の繁閑差に応じて柔軟にリソースと料金変更ができる会社を選ぶと安心です。
円滑なコミュニケーションが可能か
自社の課題を効率よく解決するためには、アウトソーシング会社と密接に連携して業務を進める必要があります。
問い合わせや資料請求時のやり取り、お試し期間の対応などで、コミュニケーションの円滑さやレスポンスの速さをチェックしましょう。またサポートに対応する時間帯や、コミュニケーション方法(チャット、メールなど)についても確認しておくと安心です。
信頼できる導入実績があるか
経理業務をアウトソーシングする場合は、重要な機密情報を預けることになるため、信頼できる外注先を選ぶ必要があります。
信頼できるアウトソーシング先を見極めるポイントは以下の通りです。
- 豊富な導入実績があるか
- 自社の業種や課題と似た導入実績があるか
- 良い口コミやレビューが多いか
豊富な導入実績がある会社は、セキュリティ体制も充実しているケースがほとんどです。また自社と似た業態や企業規模の導入実績がある会社なら、満足のいくサポートを受けられる可能性が高いでしょう。
経理業務効率化の4つのステップ
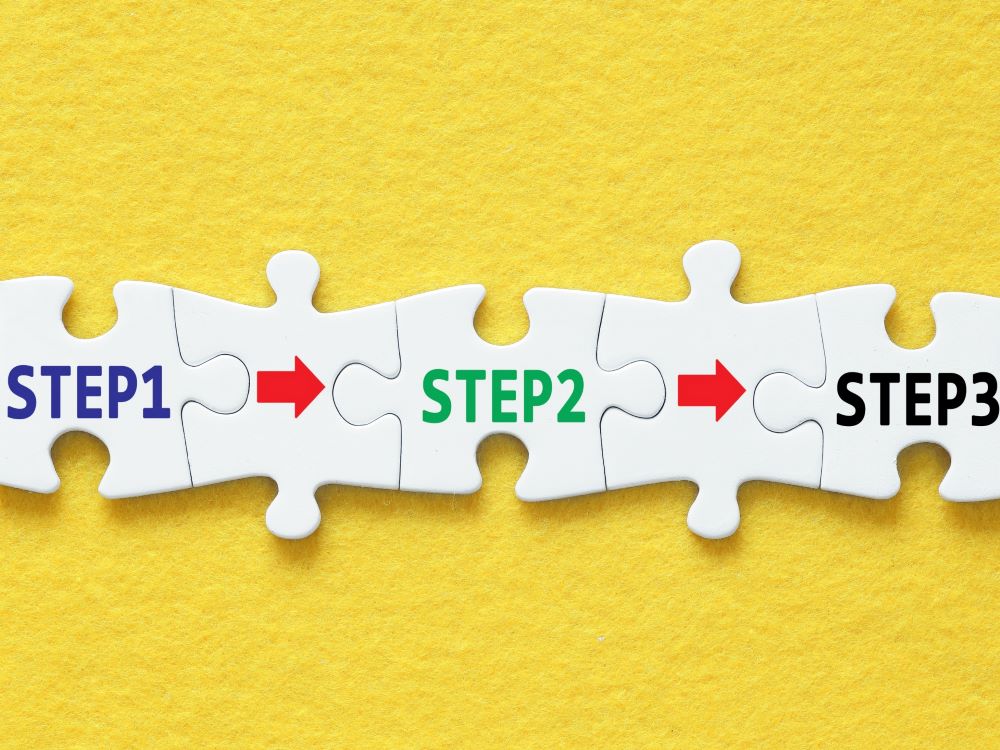
経理業務の効率化は以下の4つのステップで進めていくとスムーズです。
- 業務を洗い出し可視化する
- ECRSの4原則で業務の要否を判断する
- SMARTの法則で目標を設定する
- 成果検証を行いPDCAを回す
それぞれ見ていきましょう。
1.業務を洗い出し可視化する
はじめに経理で行っている現状業務をすべて洗い出し、可視化します。
業務の洗い出しは日次・月次・年次ごとに「誰が」「いつ」「何の」業務を行っているのかを漏れなく洗い出すことのがポイントです。
次に各業務を内容や担当部署などで分類し、体系的に整理します。
例えば 「受注内容の不備を顧客に確認する」という業務は「受注内容の修正」「修正内容の確認」「顧客への連絡」といったより細かい作業に分解できます。このように、業務を細かく洗い出すことで、非効率な部分や改善点を見つけやすくなります。
2.ECRSの4原則で業務の要否を判断する
経理の業務をすべて洗い出したら、以下のフレームワーク「ECRSの4原則」に当てはめ、一つずつ課題の解決可能性を検証します。
4原則
意味
具体的な例
Eliminate:排除
省略できる業務はないか
- 目的の明確でない定例会議
- 重要性のない日報
Combine:統合
類似業務を統合できないか
- メインバンクを決め銀行口座を一本化する
- 出席者が同じ会議は同時開催する
- 類似した業務を複数人で行っている場合、1人に集約する
Rearrange:交換
方法や順序を変更できないか
- 一部の業務をアウトソーシングする
- 業務の工程を入れ替える
- 緊急度や優先度の高い業務を優先する
Simplify:
簡素化
業務を単純化できないか
システムやITツールを導入し業務を自動化する
ECRSの4原則とは、業務効率化の課題の洗い出しに使われるフレームワークです。
可視化された課題に対し、優先順位の高いほうからE、C、R、Sの順で改善策を考えていきます。フレームワークを使えば、慣例で行っていた無意味なルーティンなど、無駄な工程の発見も可能です。
3.SMARTの法則で目標を設定する
策定された改善策に対し、以下のSMARTの法則をもとに具体的な目標を設定します。
SMARTの要素
内容
Specific:具体的な
誰が見てもわかる明確な目標にする
Measurable:計測可能な
達成度合いを数値で測定できるよう設定する
Attainable:達成可能な
願望でなく現実的な内容にする
Relevant:関連性のある
経理に関連している目標にする
Time-bound:時間制限のある
達成期限を明確にする
例えば、 ITツールで経費精算業務を自動化し、業務時短と負担軽減を図る場合「経費精算業務にかかっていた時間を、いつまでに〇%削減する」と目標を具体化します。
さらに達成可能な目標なのか、経理と関連性のある設定なのかについてもチェックしましょう。
また期限を定めることで、経理担当者のモチベーションを保ちやすくなります。
4.成果検証を行いPDCAを回す
施策を実行したら、設定した目標に対する成果検証を行い、改善のPDCAサイクルを回します。
成果検証によって、実行方法が適切だったかどうかを振り返ることができ、次の改善へとつなげられます。前に定めた数値目標に対する達成率を確認し、施策の効果を検証してください。
数値的な評価と同時に、経理担当者の心理的負担などに対する定性的な評価も必要です。アンケートやヒアリングを通じて、担当者に過度な負担がかかっていないか、業務改善に対する満足感はあるかなどを確認しましょう。
施策が一回目から上手くいくと考えず、計画(Plan)・実行(Do)・評価(Check)・改善(Action)のサイクルを繰り返す前提で考えます。定期的なチェックを繰り返し、自社に適した効率化方法を構築していくことが大切です。
経理業務効率化の成功事例
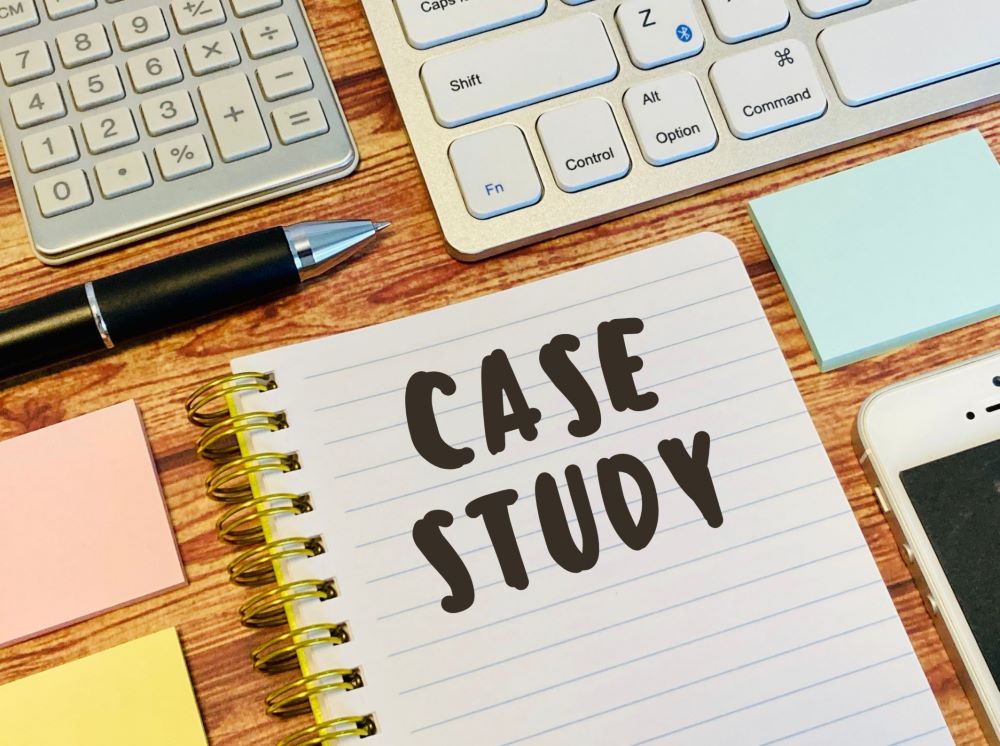
最後に経理業務の効率化を具体的にイメージできるよう、6つの成功事例を紹介します。
- 経費精算システム化で複数店舗データを一元化
- RPAと紙帳票デジタル化による大幅なリソース削減
- アウトソーシングで業務のブラックボックス化を解消
- 業務効率化でミス再発防止の仕組み化が可能に
- アウトソーシングで業務可視化とスムーズな引継ぎが可能に
- システム+アウトソーシングで急速な事業成長に対応
自社の経理業務効率化を進めるうえでの参考にしてください。
経費精算システム化で複数店舗データを一元化
全国にチェーン展開で飲食業を営む企業では、システムを導入して経費を会計ソフト上で一元管理することで、複数店舗の経費精算の効率化に成功しています。
同社では各店舗との経費精算の煩雑さが課題となっていました。各店舗から送られてくる紙の帳票には誤りが多く、差し戻しが多かったうえに、外部システムとの連携もないため膨大な再入力・転記の手間が発生していたのです。
電子帳簿保存法への対応も迫られたため、同社では経費精算システムを導入し、会計ソフトとの連携を行いました。使用頻度の高い科目を設定し、経費の仕訳データを会計処理のデータに自動で反映させるなどのカスタマイズも実施しています。
こうした帳票の電子化とデータの一元管理により、同社では経費精算の差し戻しが90%減少し、経理担当者がExcelに入力する工数を大幅に削減できました。領収書の添付も不要となり、管理負担も減少しています。
RPAと紙帳票デジタル化による大幅なリソース削減
ある中堅銅合金製造メーカーでは、RPAと帳票デジタル化サービスによる大幅なリソース削減に成功しています。
従来は取引先からの注文書や納品書を印刷したうえで、不備をチェックし基幹システムへ入力する煩雑な業務が発生していました。納品書の数が増えると、経理はパンク寸前だったとのことです。
経理部門への新規人材採用は困難と判断した同社は、経理業務を自動化し、限られた従業員をコア業務に専念させる方針に切り替えます。そこで紙帳票のデータ化サービスと、RPAによる帳票処理業務の自動化を併用し、手作業を最小限に抑え込む施策を開始しました。
施策の結果、1年で1,000時間を超えるリソース削減を実現し、さらに次の2年で全社の定型業務の工数を3割程度削減できる見通しも立ちました。そして導入1年の時点で、投資回収が見通せるほどの高い費用対効果を実感したそうです。
アウトソーシングで業務のブラックボックス化を解消
ある老舗メーカーではアウトソーシングの活用により、業務の見える化とスムーズな業務引継ぎに成功しています。
永年勤続者の多い同社では、経理担当者の定年退職にともなう業務の引き継ぎが生じました。しかし担当者しかわからない業務が多く、ブラックボックス化した膨大な経理業務の引継ぎは困難を極めます。
担当者の退職後は上長や周辺セクション、アシスタントで業務を回すものの、アシスタントもすぐに退職し、既存従業員の兼任も限界に達しました。
そこで事業運営の危機を感じた同社は、経理を中心としたバックオフィス業務全般のアウトソーシングを決断したのです。
即戦力の外部人材の活用により、同社では経理業務の属人化の解消に成功し、経理を兼任していた周辺セクションでも、本来業務の品質向上を実現できました。
業務効率化でミス再発防止の仕組み化が可能に
あるヘルスケア・美容用品の製造販売会社では、アウトソーシングの導入により経理業務のミスを軽減し、再発防止の仕組化にも成功しています。
同社では事業の成長にともなう経理の業務量急増が課題でした。自動化を進めていたものの、税法上の問題もあり、すべての帳票を電子化することはできず、スキャン業務などの煩雑な処理業務が残っていたのです。
そこで同社では紙帳票のスキャン業務にアウトソーシングを導入し、月20時間ほどかかっていた経費精算関連業務を、約1時間に圧縮することに成功しました。
また、業務効率化で余裕ができたことにより、現在ではミスの原因分析とデータ化、再発防止策の策定のプロセスを仕組化し、メンバーへの共有も可能になっています。
アウトソーシングで業務可視化とスムーズな引継ぎが可能に
あるデジタルマーケティングのスタートアップ企業では、アウトソーシングの活用で業務の可視化とマニュアル化を実現しています。
同社では早期の業務量増加が想定されたため、従業員がコア業務に集中できるよう、設立当初から経理のルーティン業務をアウトソーシングする方針を決めていました。
まず、コア業務とルーティン業務の切り分けを行った後、アウトソーシング先と連携しルーティン業務のマニュアルを作成しています。そして作成されたマニュアルにもとづき、各種資料作成や出入金管理などの業務をアウトソーシングしました。
同社ではマニュアル整備を通じて業務フローが可視化され、業務を標準化できたことにより、従業員の急な退職にもスムーズに対応できたとのことです。またアウトソーシングにより、新規採用のリスクも抑えられました。
システム+アウトソーシングで急速な事業成長に対応
あるインターネットサービス・アプリ開発のスタートアップ企業では、システムとアウトソーシングの合わせ技で急速な事業成長に対応しています。
事業拡大による社員数増加もあり、ほぼすべての従業員が経費精算を行う同社では、経理部門は常にパンク寸前の状態でした。システムを導入し効率化を試みたものの、精度に問題があったため人の手によるチェックが必要でした。
経理のリソース不足に対し、新規採用ではリスクを負うと考え、同社ではアウトソーシングの導入を決定します。業務委託先にはITリテラシーの高い会社を選定し、業務委託スタッフとは各種チャットツールやファイル共有ツールを活用し、円滑な協業体制を構築しました。
結果として同社では採用を増やさず増えた業務にも対応し、さらなる事業の拡大を実現しています。
経理業務の効率化にはアウトソーシングがおすすめ

経理業務の効率化には、ペーパーレス化やキャッシュレス化、属人化の解消、法改正への対応などの課題があります。しかしITツールやアウトソーシングを適切に活用すれば、煩雑な経理業務の効率化が可能です。
経理業務を効率化する施策を実行する際には、担当者のITリテラシーを高めると同時に、全社的な取り組みが大切です。
なお自社の経理業務に必要なリソースを、柔軟に利用したい場合にはアウトソーシングがおすすめです。
Fammアシスタントオンラインなら初月は月40,000円の料金で、必要な業務・時間・予算に合わせてハイスキルの経理人材を活用できます。業務の繁閑に合わせてリソースを柔軟に活用したい方は、ぜひFammアシスタントオンラインへご相談ください。
\ 月額¥60,000~利用できる /
資料「Fammアシスタントオンラインサービス」
を無料ダウンロード

