業務委託のトラブル事例5選|予防策や業務委託契約書作成のポイントも解説
-
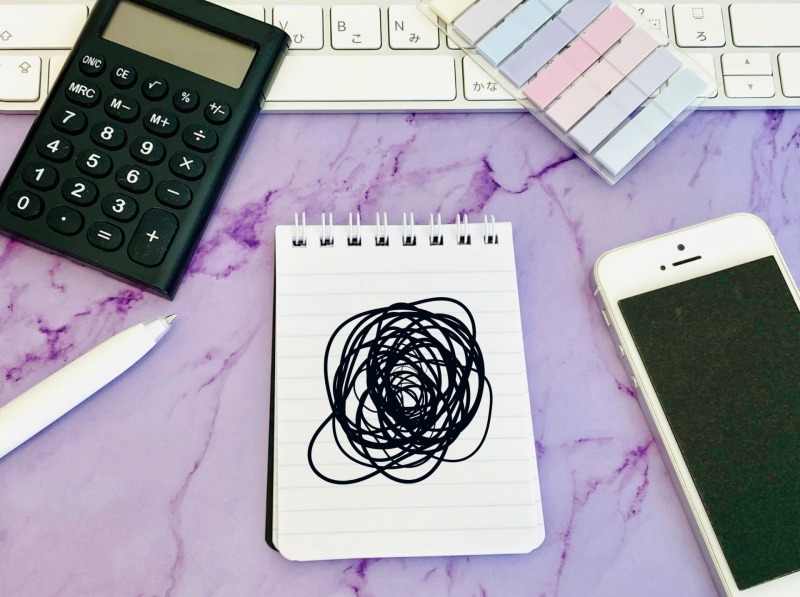
-
自社の業務を外部の事業者に依頼する業務委託は、コスト削減や生産性向上など、多くのメリットがあります。一方で、納期遅延や品質不良などのトラブルが発生するリスクがあり、注意が必要です。
本記事では、業務委託を検討している企業向けに、業務委託でよくあるトラブルの事例を5つ紹介します。また、トラブルの予防策や業務委託契約書作成のポイントも解説するので、ぜひ参考にしてください。
この記事でわかること
- 業務委託でよく起こるトラブルの事例
- 業務委託のトラブル予防策
- 業務委託するならFammアシスタントオンラインがおすすめ
\ 月額¥40,000~利用できる /
資料「Fammアシスタントオンラインサービス」
を無料ダウンロード目次
業務委託契約とは
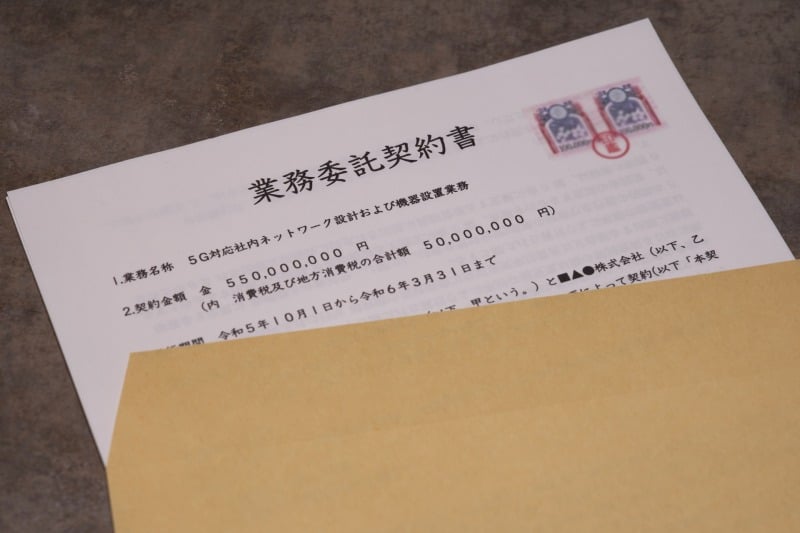
業務委託契約とは、委託者(依頼する側)の業務を外部の受託者(依頼を受ける側)に依頼する際に締結する契約です。
委託者が依頼した業務について、受託者は独立して業務を遂行し、その業務の遂行または成果物に対して報酬を受け取ります。
契約した範囲の業務が完了し、報酬が支払われた時点で契約関係は終了します。その後、委託者と受託者の合意があれば、継続して同じ業務を依頼することも可能です。
なお、民法では典型契約として、請負契約(民法第632条)や委任契約(民法第643条)、準委任契約(民法第656条)が定められていますが、業務委託契約という用語は登場せず、明確な定義はありません。
雇用契約との違い
雇用契約とは、労働者が使用者(雇用主)との間で結ぶ契約であり、労働者は使用者に労働を提供する対価として報酬を受け取ります。
雇用契約は民法第623条に規定されており、雇用契約を締結することで、労働者は労働基準法や労働契約法によって保護されます。
業務委託契約と雇用契約の大きな違いは、契約する当事者の間に使用従属性(主従関係)があるかどうかです。業務委託契約には使用従属性がなく、受託者は基本的に独自の判断で業務を遂行できます。一方、雇用契約の場合は、労働者は使用者の指揮命令に従う義務があります。
業務委託契約の類型

業務委託契約には3つの種類があります。
業務委託契約を結ぶ際は、どの種類の契約に近いのかを確認した上で、契約書を作成するようにしましょう。
- 請負契約
- 委任契約
- 準委任契約
請負契約
請負契約とは、受託者が成果物の納品を約束し、委託者はその成果物に対して報酬を支払う契約です。請負契約の特徴は、受託者が委託者から依頼された仕事を完成させる義務を負うことです。そのため、納品した成果物に欠陥があった場合、委託者は受託者に修正や減額を請求できます。
次のような業務委託は、請負契約に該当します。
請負契約の例
業務の例
Webサイト制作
企業が外部のWebデザイナーにWebサイト制作を依頼する。契約で定めた方法でデザイナーが成果物を納品し、それに対して企業が報酬を支払う。
システム開発
企業がIT企業にシステム開発を発注する。IT企業が事前に合意した仕様に沿って、システムを開発し、納品する。それに対して委託者は報酬を支払う。
建築工事
顧客が建設会社にオフィスの設計・施工を依頼。建設会社は、完成したオフィスを引き渡し、顧客はそれに対して報酬を支払う。
委任契約
委任契約とは、法律行為を委託する契約を指します。
委任契約の代表的な例として、弁護士への訴訟委任や司法書士に登記業務を依頼するなどが挙げられます。
委任契約は請負契約と異なり、成果物の完成を目的とするのではなく、誠実に業務に取り組む義務(善管注意義務)を負うことが特徴です。
例えば、弁護士は訴訟に勝訴することを約束できませんが、法律の専門家として最善を尽くす責任があります。
準委任契約
準委任契約は、委任契約に準ずる契約として規定されています。準委任契約は委任契約と同様に、受託者は適切に業務を遂行する義務を負います。
委任契約と異なる点は、準委任契約は法律行為以外の業務を委託する契約です。
以下は、準委任契約の例です。
準委任契約の例
業務の例
システム保守
エンジニアがシステムの監視や障害対応など、必要に応じたシステム保守を行い、作業工数(人日など)に応じて報酬を支払う。
コンサルティング
経営戦略や人事戦略など、専門的なアドバイスを提供し、相談に対応した時間分の報酬を支払う。
事務代行サービス
データ入力やメール対応など、業務の遂行に対して報酬を支払う。
業務委託のメリット

本章では、業務委託の代表的な3つのメリットを解説します。
- コア業務に集中できる
- コストを削減できる
- 専門性を活用できる
コア業務に集中できる
コア業務とは、企業の利益や成長に直結する業務を指します。例えば、新製品の開発や営業戦略の立案などがコア業務に該当します。
しかし、企業を安定して運営するには、定型的な事務作業など、企業の成長には直結しない多くのノンコア業務も必要です。このようなノンコア業務を業務委託すれば、経営者や従業員はコア業務に集中する時間を確保できます。
コア業務に集中できる環境を整備することは、従業員のモチベーション向上にもつながり、より挑戦的な課題への取り組みや高い成果が期待できます。
コストを削減できる
業務委託では、従業員を雇用する場合と異なり、労働法が適用されません。そのため、社会保険料や福利厚生費などを支払う必要がなく、人件費を削減できます。また、企業の繁忙に合わせて、業務委託の規模を調整できるため、過剰な人員配置を避けられ、コスト効率が高まります。
専門性を活用できる
自社では対応ができない専門的な業務などを、外部の事業者に委託することで、その事業者が持つ経験やノウハウを活用できます。また、業務を委託することで、自社にはないアイデアや視点を取り入れられ、業務の品質向上も期待できます。
業務委託のデメリット
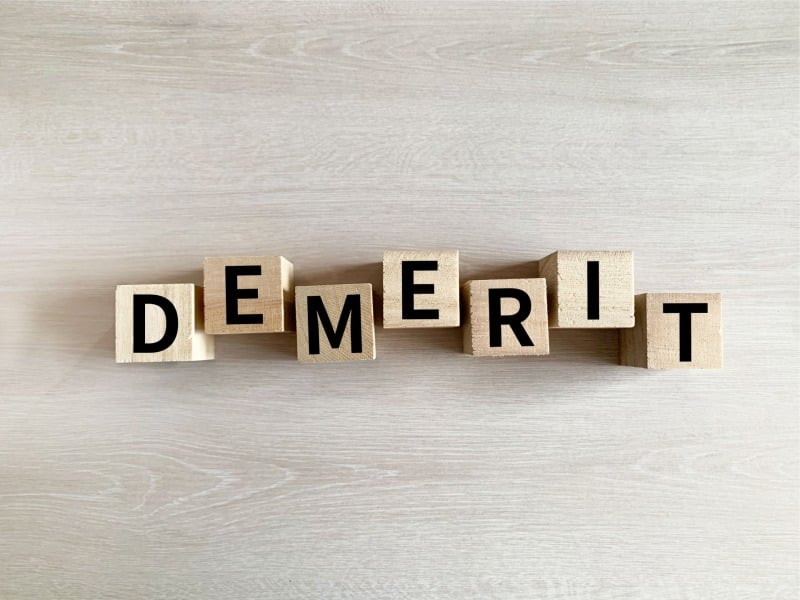
業務委託にはさまざまなメリットがある一方で、いくつかのデメリットもあります。
本章では、業務委託のデメリットについて解説します。
- 社内にノウハウが蓄積されない
- 業務の品質が均一化されにくい
社内にノウハウが蓄積されない
長期的に業務委託する場合、従業員がその業務に携わる機会を持てず、社内にノウハウが蓄積されない可能性があります。業務を委託している事業者が、突然サービスの提供を中止するなど、不測の事態が発生した場合、社内に対応できる人材がいなければ、業務が停滞する危険があります。
業務の品質が均一化されにくい
業務を委託する事業者によってスキルや経験が異なるため、同じ業務を複数の事業者に発注した場合、成果物の品質にばらつきが生じやすくなります。また、業務の迅速さや丁寧さなどの対応も異なることが多いため、自社での業務進捗管理が難しくなり、最終的な品質管理に影響を及ぼすリスクもあります。
業務委託で発生しやすいトラブルの事例
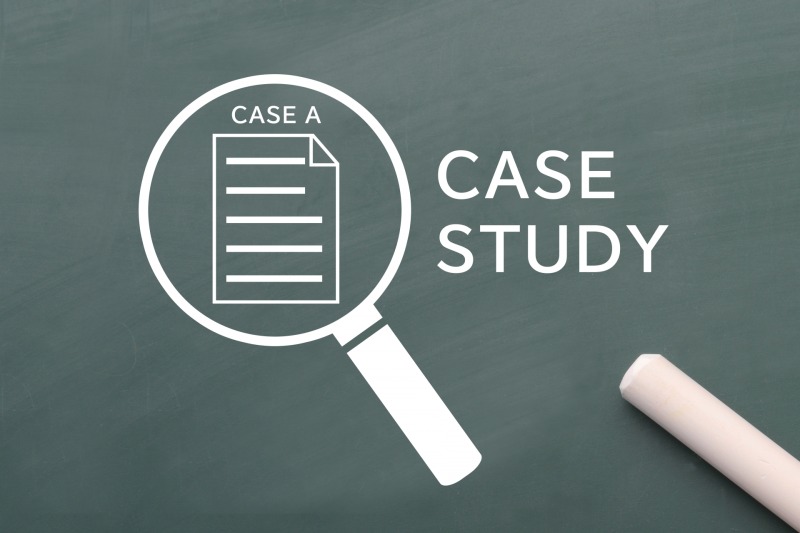
本章では、業務委託で発生しやすいトラブルの事例を5つ紹介します。
次章で具体的な予防策を解説するので、あわせて参考にしてください。
- 事例1:納品の前に連絡が取れなくなった
- 事例2:納期が遅延した
- 事例3:成果物の品質が要件を満たしていない
- 事例4:追加費用を請求された
- 事例5:機密情報が漏えいした
事例1:納品の前に連絡が取れなくなった
納品の前に連絡が取れなくなるトラブルは、特にフリーランスなどの小規模事業者との業務委託で発生しやすい事例です。
受託者と連絡が取れなくなる理由はさまざまですが、以下のような原因が考えられます。
- 担当者の体調不良
- 別の案件が忙しく、連絡が滞っている
- 経営状況の悪化による廃業
- 通信システムで障害が発生している など
このような状況が発生した場合、業務計画の大幅な見直しが必要なため、事前に対策を講じることが重要です。
事例2:納期が遅延した
納期遅延の発生は、委託先の進捗管理不足やリソース配分が適切でなかった場合に、度々起こるトラブルです。一方、委託者側でも、急な仕様変更の要求や確認作業の遅れなどが原因で、全体のスケジュールを遅延させてしまう場合もあります。そのため、委託者と受託者の双方が、継続的にスケジュールを確認しながら業務を進行させることが必要です。
事例3:成果物の品質が要件を満たしていない
成果物が期待した品質を下回るトラブルは、以下のような理由で発生する可能性があります。
- 成果物への要件定義が不明確であった
- 受託者のスキル不足
- 委託者・受託者間でのコミュニケーション不足
- 委託者が中間チェックする体制がなかった など
成果物の品質が低かった場合、受託者に修正を依頼する必要があり、追加の時間やコストが発生する可能性があります。このような事態を避けるために、業務委託をする際は、明確な要件定義や事前に受託者のスキルを確認するなどの対応が必要です。
事例4:追加費用を請求された
業務委託契約を締結した後、受託者から追加の費用を請求される場合があります。委託者が追加費用分の予算を確保していなかった場合、プロジェクトを中断しなくてはならない可能性があり、注意が必要です。
受託者が追加費用を請求する背景には、次のような要因が挙げられます。
- 修正作業に対する費用が含まれていなかった
- 途中で仕様が変更され、新たな作業が発生した
- 予期せぬ技術的な問題が発生し、作業量が増えてしまった など
契約時に作業の範囲や修正が必要となった場合の費用について、あらかじめ条件を定め、予算超過を防ぐことが重要です。
事例5:機密情報が漏えいした
機密情報とは、顧客データや財務データ、製品設計図など、第三者に漏えいした場合に企業や個人に不利益をもたらす重要な情報を指します。
受託者が機密情報を漏えいさせたとしても、委託側の企業イメージ低下や法的責任追及の可能性があります。そのため、機密情報を外部に持ち出す必要がある場合は、常に情報漏えいの危険があると認識することが重要です。
業務委託で機密情報が漏えいしてしまう背景として、以下のような要因が考えられます。
- 機密情報の取扱いについて事前に取り決めていなかった
- 受託者の情報管理が不適切であった
- 安全性の低い共有ツールなどを使用していた
- 業務に使用していたパソコンのセキュリティソフトが更新されておらず、サイバー攻撃を受けた
- USBなどの記録用媒体を紛失した
- 受託者が意図的に第三者に情報を提供した など
委託者と受託者の双方で、何が機密情報に該当するのかを共有し、運用ルールを徹底する必要があります。
業務委託のトラブル予防策

本章では、業務委託でのトラブルを未然に回避するためのポイントを解説します。
- 業務管理体制を確認する
- 効果的なコミュニケーション体制を構築する
- 小規模な業務から委託する
- コスト管理を行う
- 情報セキュリティ対策が十分か確認する
- 明確な仕様書を作成する
- 書面で契約を取り交わす
業務管理体制を確認する
受託者の業務体制を確認することは、成果物の品質を確保し、納期遅延などのトラブル防止につながります。
受託者の業務体制を確認する際は、以下のような点に注意すると良いでしょう。
確認事項
概要
責任者・担当者の役割
だれがどの業務を担っているのかを明確にし、業務の漏れや重複を避ける。また、品質・予算・スケジュールなど、業務を進める上で重要な部分の責任者を決定する。
業務フロー
どのような工程で業務を進めるのかを確認する。また、委託者側で必要な作業やチェック期間などを洗い出す。
進捗管理の方法
委託者・受託者で共有できるタスク管理ツールの有無やスケジュールの更新方法などを確認する。
問題発生時の対応
予期せぬトラブルが発生した場合に、対応できるリソースやスケジュールの余裕があるかを確認する。
効果的なコミュニケーション体制を構築する
業務委託でトラブルが発生する要因の1つとして、委託者と受託者間のコミュニケーション不足や認識の不一致が挙げられます。効果的なコミュニケーション体制を構築することで、問題が発生した場合でも早期に対策でき、影響を最小限に抑えることが可能です。
効果的なコミュニケーション体制を構築するためには、以下のようなポイントがあります。
ポイント
概要
連絡窓口を設置する
連絡窓口となる担当者を定め、情報伝達の経路を明確にし、情報の抜け漏れを防ぐ。万が一、窓口担当者と連絡がつかなかった場合の代理についても決定しておく。
コミュニケーション手段を確認する
日常的な確認や報告はチャットツール、重要な決定は対面で行うなど、場面に応じたコミュニケーション手段を決定する。
定期的にミーティングを開催する
定期的なミーティングで、進捗や品質を確認する。問題となりそうな事案についても早めに共有し、対策を協議する。
議事録を作成する
ミーティングなどで決定した事項や不確定要素について、誰がいつまでに対応するのかを明確にする。議事録を関係者に共有し、認識の不一致を防ぐ。
小規模な業務から委託する
小規模な業務からの段階的な業務委託は、受託者のスキルや業務の進め方を確認する手段として有効です。期待通りの成果が確認できた後、業務委託の規模を拡大すれば、リスクを最小限に抑えられます。
以下のようなポイントに注意し、小規模な業務委託を通じて、自社にとって適切な委託先であるかを確認しましょう。
確認事項
概要
業務遂行能力
・成果物や業務の品質は十分か
・納期は守られているか
・修正を依頼した場合の対応はスムーズか
コミュニケーション
・適切な頻度で進捗報告があるか
・認識の不一致は起きていないか
業務の進め方
・自社の業務フローに対応が可能か
・業務の進め方に無駄はないか
コスト管理を行う
適切にコスト管理を行うことで、予算の超過や不必要なコストの発生を防ぎ、業務委託を円滑に進められます。
以下は、適切なコスト管理を行うためのポイントです。
ポイント
概要
明細な見積書を入手する
作業範囲を明確にし、費用を確定させる。どのような修正が発生した場合に追加費用が発生するのかを確認する。
別の事業者の見積書と比較する
別の事業者に委託した際の見積書と比較し、適正な費用を把握する。費用に差があった場合は、作業や対応の範囲を明確にし、自社が必要とする作業やサービスが含まれているかを確認する。
情報セキュリティ対策が十分か確認する
情報漏えいのトラブルを防ぐためには、情報セキュリティ対策を適切に講じている受託者を選定することが重要です。
情報セキュリティ対策について確認するポイントには、次のようなものがあります。
- プライバシーマークやISO/IEC 27001などの外部認証取得状況
- 定期的なセキュリティ監査の実施
- 書類やデータの管理方法
- 通信の暗号化の実施
- オフィスなどへの入室管理
- 情報セキュリティに関する定期的な研修の実施 など
また、業務委託を開始する前に、受託者と秘密保持契約(NDA)を締結し、情報漏えいが発生した場合の責任範囲を明確化しましょう。
明確な仕様書を作成する
業務委託における仕様書とは、業務の内容や成果物に必要な機能、数量、納期などの詳細を書面にしたものです。委託者と受託者の間で認識の不一致を防ぐために、明確な仕様書を作成し、双方が合意することが重要です。
また、前章で解説した通り、請負契約では「業務の完成」、準委任契約では「適切な業務遂行」を求めることに違いがあります。そのため、それぞれの契約の特性に応じた仕様書を作成する必要があります。
業務委託で仕様書を作成する際は、以下の点を明記するようにしましょう。
請負契約(成果物の納品)
準委任契約(業務遂行)
業務内容
成果物の内容(Webサイト制作やシステム)
遂行する業務内容(会議参加や書類処理など)
納期
納品期日の設定(〇〇年〇月〇日など)
業務時間の設定(週〇時間、月〇回など)
品質基準
成果物の性能、数量、納品形式などの詳細
業務遂行レベルを設定(業務の正確性や処理速度など)
変更対応
仕様を変更した場合の合意方法を設定
業務範囲変更の手続きやルールの設定
書面で契約を取り交わす
民法では口頭での契約の成立を認めていますが、業務委託をする場合は必ず書面で契約を締結しましょう。
万が一、トラブルが発生した際に、契約内容を証明する書面があれば、早期に紛争を解決できます。また、契約の途中で変更や追加があった場合にも、双方の合意があれば「覚書」や「変更契約書」として書面を取り交わします。
業務委託契約書を作成する際のポイント

本章では業務委託契約書を作成する際のポイントについて解説します。
- 契約書に記載すべき項目を網羅する
- あいまいな表現を避ける
- トラブルが発生した場合を想定する
契約書に記載すべき項目を網羅する
業務委託契約書に記載する項目が不十分な場合、責任の所在が不明確になり、解決が困難になる危険性があります。このようなリスクを避けるため、業務委託契約書を作成する際は、必要な事項を網羅し、双方の義務と権利を明確にしましょう。
以下は、業務委託契約書を作成する際に記載すべき主要な項目です。
項目
概要
委託業務の内容
業務委託の具体的な業務の内容や成果物を記載する。
契約期間
契約の開始日と終了日を記載する。
委託料
委託する業務に対する報酬額を記載する。
支払条件
委託料を支払う期日や支払い方法を記載する。
知的財産権の帰属
成果物に知的財産権が発生した際に、誰に権利が帰属するのかを記載する。
再委託
受託者がさらに第三者に業務を委託する場合のルールを記載する。
秘密保持義務
業務上知り得た情報を第三者に開示しない義務を記載する。
反社会的勢力の排除
契約の当事者が反社会的勢力に属していた場合、もう一方の当事者は契約を解除できる条項を記載する。
契約の解除
契約を解除できる条件や期間、手続きを記載する。
損害賠償の範囲
当事者の一方による契約違反や契約解除によって発生した損害に対する責任や賠償額の上限を記載する。
禁止事項
業務を行う際に禁止したい事項があれば記載する。
管轄裁判所
紛争が生じた場合に、第一審の裁判所をどこにするかを記載する。
以上の項目以外にも、業務内容や条件に応じて、必要な項目を明記するようにしましょう。
あいまいな表現を避ける
業務委託契約書を作成する際に、あいまいな表現を避けることで、当事者間の認識を統一しトラブルの発生を防げます。
以下は、契約書作成時にあいまいな表現を避けるためのポイントです。
ポイント
概要
具体的な表現を用いる
具体的な数値、期限、手順などを明記する。
専門用語を定義する
専門用語を使用する際は、その定義を契約書内に記載する。
第三者が見ても理解できる内容にする
契約当事者以外でも理解できるように、平易な言葉で記載する。
トラブルが発生した場合を想定する
業務委託契約書を作成する際に、実際にどのようにトラブルを解決するかを想定することは、リスクを最小限に抑え、問題を早期に解決するために重要です。
トラブルが発生した際の解決策には、次のようなものがあります。
対応策
概要
協議
契約当事者間での話し合い。
調停・ADR
裁判所による調停、あるいは第三者機関によるADR(あっせん、調停、仲裁)による解決。
訴訟
管轄の裁判所に訴訟を提起し、裁判官に判断を委ねる。
どのような手順でトラブルを解決するのか、契約当事者間で合意した上で契約を締結するようにしましょう。
業務委託でトラブルが発生した場合の対処法

本章では、業務委託でトラブルが発生した場合に、円滑に問題を解決するための対処法を解説します。
- トラブルが発生した背景事情を検証する
- 関係者でトラブルの要因を議論する
- 弁護士に相談する
トラブルが発生した背景事情を検証する
トラブルが発生した背景事情の検証は、トラブルの根本的な原因を特定し、再発防止策を講じるために重要な対応です。
トラブル発生の背景事情を把握するためには、次のような検証方法が有効です。
検証方法
概要
契約関連書類の確認
契約書、仕様書、見積書など、契約に関する全書類を確認し、契約内容を把握する。
業務記録の確認
メール、議事録、日報など、業務遂行状況を示す記録を確認し、どの時点で問題が発生したのかを把握する。
関係者へのヒアリング
委託者、受託者それぞれの担当者から事情を聴取する。
検証の過程で得られた情報は時系列で整理し、問題の全体像を把握するようにしましょう。また、関係者の発言や行動の経緯を追うことで、責任の所在を明確にすることも期待できます。
関係者でトラブルの要因を議論する
委託者と受託者の双方で、トラブルの要因について議論することは、多角的に解決策の検討ができます。また、対等な立場で議論することで、合意形成を図りやすく、問題の早期解決にもつながります。
関係者で議論をする際は、感情的にならず事実に基づき冷静に話し合うことが重要です。また、それぞれの立場を尊重し、相手の意見に耳を傾ける姿勢を取ることで、効果的に議論を進められます。
弁護士に相談する
弁護士に相談することで、契約内容をもとに、どのような権利と義務があるのかを明確にでき、訴訟に発展した場合のリスクについてもアドバイスをもらえます。
また、当事者間での話し合いが難しい場合、弁護士が代理人として交渉することで、感情的な対立を避け、円滑な解決が期待できます。
トラブルを防いで円滑に業務委託をしよう

業務委託は、外部の事業者の専門的な知識やスキルを活用でき、企業を成長させるために有効な手段です。
しかし、納期の遅延や成果物の品質が低いなど、さまざまなトラブルが発生するリスクもあります。このようなリスクを避けるためには、業務委託で起こりやすいトラブルを理解し、適切な予防策を講じることが重要です。
業務委託を考えているなら、Fammアシスタントオンラインがおすすめです。
高いスキルと知識を持つスタッフが、幅広い業務に対応します。
月額4万円から業務委託を開始できるので、業務委託を検討しているなら、試してみてはいかがでしょうか。
\ 月額¥40,000~利用できる /
資料「Fammアシスタントオンラインサービス」
を無料ダウンロード

