繁忙期に向けた対策と乗り越え方|準備と閑散期にやるべきことも解説
-

-
繁忙期は年間で特に業務が煩雑な時期であると同時に、売上を伸ばすチャンスでもあります。
しかし社内に十分なリソースがなければ、繁忙期の需要を売上につなげることができません。人員不足などにより顧客の問い合わせや要望に応えきれず、お悩みの方も多いのではないでしょうか。
繁忙期のリソースを適切にコントロールすることで、業務品質と顧客満足度を高められ、利益率の向上につなげられます。
本記事では繁忙期の課題と対策、閑散期に行う事前準備について解説します。繁忙期の売上を伸ばしたい方は、ぜひチェックしてみてください。
この記事でわかること
- 繁忙期の課題とスムーズに乗り越える方法
- 繁忙期の事前準備と繁忙期後に行うこと
- 繁忙期対策にアウトソーシングを活用するならFammアシスタントオンラインがおすすめ
\ 月額¥60,000~利用できる /
資料「Fammアシスタントオンラインサービス」
を無料ダウンロード目次
繁忙期とは

はじめに繁忙期と、繁忙期の対義語である閑散期の定義を解説します。
- 繁忙期とは仕事が煩雑な時期のこと
- 閑散期とは仕事が落ち着いている時期のこと
繁忙期とは仕事が煩雑な時期のこと
繁忙期とは、年間のうち仕事が集中し煩雑になる時期のことです。通常、数週間から数カ月の中長期を指し、1日単位で業務が集中する日を指すわけではありません。
繁忙期の時期や回数は業種や企業によって異なり、決算の時期や回数、商業的なかき入れ時などにより決まります。
一般に繁忙期は利益の出る時期に当たりますが、同時に社内のリソースが不足しやすい時期でもあります。業務量の増加により従業員に過剰な業務負荷がかかりやすく、業務品質に影響を及ぼす恐れもあります。
そのため、繁忙期の乗り切り方について、頭を悩ませている企業は少なくありません。
閑散期とは仕事が落ち着いている時期のこと
閑散期とは繁忙期の逆で、仕事が落ち着いている時期のことです。
閑散期には時間的な余裕が生まれやすいため、繁忙期にできない中長期的施策などを実施できる時期でもあります。一方で、閑散期は売上が伸び悩む時期でもあるので、資金不足に陥らないよう堅実な集客活動と成果が必要です。
なお、顧客の閑散期を把握しておけば、アポイントやヒアリングの時間を取りやすいため、コミュニケーションの円滑化が可能です。このように閑散期は繁忙期の利益拡大に向け、新しい施策を始める時期とも捉えられます。
繁忙期と閑散期に差がある業種

一般に繁忙期と閑散期に差があると言われる業種は以下のとおりです。
業種
繁忙期
会計・税務業
2月〜3月(確定申告)、5月〜6月(法人税の申告)
飲食業
12月(忘年会)、3月〜4月(歓送迎会)、4月〜5月(GW)
観光・宿泊業
7月〜8月(夏休み)、12月〜1月(年末年始)
レジャー業
7月〜8月(夏休み)、3月〜5月(GW)
ブライダル業
3月〜6月(春婚)、9月〜11月(秋婚)
小売業
12月(歳末セール)、3月(決算セール)
アパレル業
3月〜5月(春物)、9月〜11月(秋物)
物流・運送業
12月(年末商戦)、3月(年度末)
建設業
2月〜3月(年度末)、9月〜11月(秋の需要期)
不動産業
1月〜3月(年度末移動)、9月〜11月(秋の引越しシーズン)
上記のように、繁忙期の時期と繁閑差が生じる理由は業種により異なります。
例えばレジャー・宿泊業の大型連休、飲食業の宴会シーズンなどは顧客ニーズによってかき入れ時が生じ、それ以外の月は比較的業務が落ち着く傾向です。同様に、小売業やアパレル業、不動産業なども商材の売れる時期によって決まります。
一方、会計・税務業の業務集中期は税の申告時期と年末調整、決算期です。建設業では予算の決算前、新年度竣工に向けた需要による繁忙期が生じます。
繁忙期に起こりがちな課題

ここで繁忙期に起こりがちな課題について解説します。
- 時間外労働が増える
- 作業のミスが増える
- 離職リスクが高まる
- 需要を100%売上につなげられない
- 顧客満足度が低下する
時間外労働が増える
繁忙期には人手不足が発生しやすく、時間外労働が増えがちです。
大幅に増加する業務量に対し平常通りの人員で臨んだ場合、リソースの不足分を既存従業員の残業や休日出勤で補わなければなりません。
休みなく働き心身に負担がかかり続けた従業員は、体力やモチベーションが続かなくなる恐れがあります。従業員の意欲低下は仕事に対する意識にも影響を及ぼす可能性があり、早く業務を切り上げようと手抜きする者が現れるかもしれません。
時間外労働が増えることによって、人件費が増加すれば利益率は低下するため、繁忙期の業務改善は避けて通れないでしょう。
作業のミスが増える
忙しいあまり業務にミスが生じやすくなることも、繁忙期に起こりがちな課題です。
繁忙期には従業員が業務のスピードアップを迫られ、マルチタスク状態に置かれることも少なくありません。
従業員の焦りと疲れが募り、ダブルチェックを行う余裕もない状態では、閑散期では考えられないミスが起こるケースもあります。また、忙しさのあまり「誰かがやっているだろう」と、ちょっとした確認が疎かになり、業務の抜け漏れが生じることもあるでしょう。
多忙な環境下で見過ごされた問題が、後にクレームなどに発展するリスクもあるため、未然に対策が必要です。
離職リスクが高まる
繁忙期で過酷な勤務状況が続くと、従業員の離職リスクが上昇します。
連日の残業や休日出勤による体力の低下や、仕事が終わらないストレスから、体調を崩し欠勤する従業員も出てくるでしょう。欠勤が生じた結果、他の従業員の負担が増えると、不満が連鎖する悪循環に陥りがちです。
ワークライフバランスが重視される近年においては、労働環境の悪化が従業員のモチベーション低下の主要な要因となっています。長時間労働や休日出勤、スタッフ欠勤時のフォロー体制が確立されていない組織においては、退職を考える者が増加する恐れがあります。
需要を100%売上につなげられない
繁忙期に適切な業務体制を整えていなければ、市場の高い需要を100%売上につなげられない可能性があります。
業務量が増えているにもかかわらず、通常通りの人員で対応せざるを得ない場合には、人手不足によって売上向上に必要な業務を賄いきれないことがあります。
稼ぎ時で顧客のニーズが増えているのに、人手不足で求められる商品やサービスの提供が間に合わないために、売上の機会を損失してしまうケースも少なくありません。
顧客満足度が低下する
繁忙期の多忙な業務が顧客満足度を低下させてしまうケースもあります。
顧客側は基本的に自社の繁忙期を理解しているわけではないため、平常時の品質のサービスを求めてきます。リソース不足で商品やサービスの品質が低下してしまうと、顧客は不満を感じるでしょう。
場合によってはクレームを受けたり、リピートが減少したりする恐れもあります。提供したサービスに対し悪い口コミを書かれるようなことがあれば、企業のイメージダウンにもつながりかねません。
繁忙期をスムーズに乗り越える方法
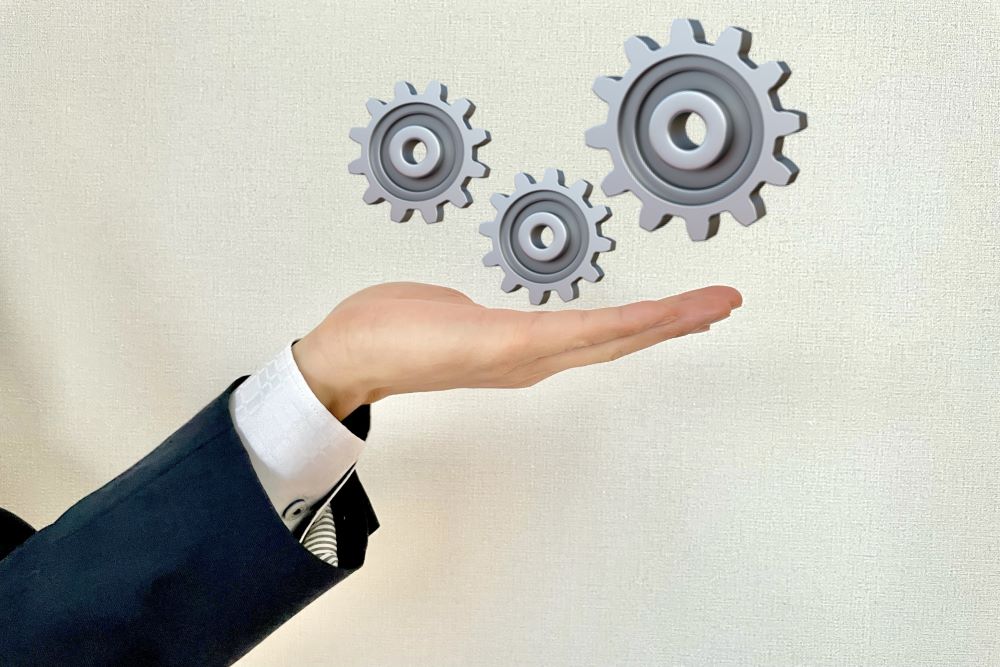
ここでは繁忙期のさまざまな課題をクリアし、スムーズに乗り越えるための方法を解説します。
- オペレーションに優先順位をつける
- 明確な役割分担を決めておく
- 他部署に応援を要請する
- 短期のアルバイト・人材派遣を活用する
- アウトソーシングを活用する
- ITツールで業務を効率化する
オペレーションに優先順位をつける
オペレーションに優先順位をつけることで、繁忙期のスムーズな業務運用が可能になります。
当日のタスクに優先順位を付けるには、以下の手法が役に立ちます。
優先順位を付ける手法
内容
アイゼンハワー・マトリクス
緊急度・重要度の両面から優先順位を判断
タイムボックシング
タスクに一定の時間枠を設定して集中する時間管理手法
パレートの法則
「80:20の法則」
※「特定の要素の20%が全体の80%の成果を生み出している」という経験則。成果を出している特定の要素に注力し高い結果を出す手法。
優先順位をつけてタイムマネジメントを行うコツは、タスクを細分化することです。仕事に取り掛かる際の心理的負担が軽減され、効率よく業務を進められる効果があります。
アイゼンハワー・マトリクスの手法では、各タスクを緊急度・重要度の両面から評価し「緊急かつ重要な業務」を最優先に取り組みます。
タイムボックシングは、例えば「10:00〜11:30顧客対応」「11:45〜13:00報告書作成」のように、タスクに時間枠を設けることで作業に集中する手法です。
優先順位の低い雑務に取り組む時間を決めておき、まとめて処理することで優先順位の高い業務に集中でき、作業効率を高められます。
パレートの法則を用いた具体例は「もっとも売上に貢献するサービス・商品および最重要顧客にリソースを集中する」などです。
上記の手法を適宜組み合わせ、業務の優先順位付けを徹底しましょう。
明確な役割分担を決めておく
繁忙期をスムーズに乗り越えるためには、チームの役割分担を明確にし、綿密なコミュニケーションを取り合うことが大切です。
メンバーの役割分担と責任範囲を重複・漏れなく明確に決めておくことで、各自の動きに迷いがなくなります。1日の始まりや半日単位で短時間のスタンドアップミーティングを行い、その日の目標と流れを共有しておきましょう。
期間中はタスク管理ツールなどで進捗を可視化し、チーム全員がリアルタイムの状況を把握できる状態をつくると、各自が効率的に動きやすくなります。
なお、状況によっては柔軟なタスクの再配分も必要です。問題が発生した場合の報告方法(誰に、どのように伝達するか)を明確にし、迅速な意思決定ができる体制も構築しておきましょう。
他部署に応援を要請する
繁忙期の人員不足に対し、他部署の応援を要請して乗り切ることも一つの方法です。
部署によって繁忙期が異なる場合は、繁忙期の応援を他部署に依頼が可能です。比較的ゆとりのある部署に応援を依頼できれば、社内リソースで増えた業務に対応できるため、追加の経費がかからないメリットがあります。
ただし、他部署のスタッフは依頼する業務に慣れているとは限らないため、新たに指導や引継ぎが必要となり、スキル不足でかえって業務効率が落ちるケースもあるでしょう。そのため他部署のスタッフに依頼する業務は、単純な業務や標準化された業務のみに制限するほうが適切です。
なお、部署を横断して業務に取り組む際には、後の関係が悪化しないよう十分なコミュニケーションと配慮が必要です。
短期のアルバイト・人材派遣を活用する
繁忙期の人員が不足する場合に、単発派遣や短期アルバイトなどを手配して乗り切る方法もあります。
人材派遣やアルバイトなら、正社員で通年雇用するよりも大幅にコストを抑えることが可能です。近年はスポットのアルバイトで柔軟な働き方をする方も増えているので、業務量がピークの日などに活用するとよいでしょう。
ただし、一時使用の人材派遣やアルバイトは当人に専門の経験や資格がない限り、専門性の高い仕事の依頼は困難です。短期の臨時雇用者についても、基本的に標準化された作業しか依頼できません。
また、指導や引継ぎが都度必要となるため、指導者が現場を抜ける時間も考慮しましょう。
アウトソーシングを活用する
繁忙期のみ人材を確保したい場合は、アウトソーシングの活用がおすすめです。
アルバイトとの違いは、業務に適したスキルを持つ人材をアサインしてもらえるため、標準化された業務以外も依頼でき、一定の高い業務品質が期待できる点です。
時間当たりの費用はアルバイトより高額になるものの、アウトソーシングでは必要なスキルに特化して必要な時間だけを柔軟に依頼できるため、人件費の無駄が生じません。結果として高い費用対効果が望めます。
アウトソーシング会社によっては、短期間のトライアルを使える場合があるので、依頼したい業務に対応しているか、問い合わせてみることをおすすめします。
ITツールで業務を効率化する
繁忙期に備えてITツールを導入し、一部の業務を自動化するのも一つの方法です。
ITツールで単純作業や定型業務を自動化できるため、繁忙期の業務負荷を大幅に軽減できる可能性があります。会社や業種ごとに解決すべき課題は異なりますが、一般的には以下の業務効率化ツールが多く活用されています。
- ビジネスチャットツール
- タスク・プロジェクト管理ツール
- Web会議ツール
- ペーパーレス化ツール
- RPAツール
- SFA・CRM・MAツール
- オンラインストレージ・ファイル共有ツール
- ナレッジ共有ツール
自社の業務課題に合わせて上記のツールを活用すれば、生産性の向上や業務コスト削減につながります。時間のかかる作業を自動化できるため、繁忙期の従業員の労働負担を軽減できるでしょう。
繁忙期の前にやっておくべき対策

繁忙期をスムーズに乗り越えるためには、事前の準備が欠かせません。ここでは繁忙期を迎える前に、やっておくべき準備や対策を紹介します。
- 人員計画を策定する
- 業務プロセスを見直す
- 在庫管理体制を整備する
- システム・ツールの導入・整備を行う
- 従業員トレーニングを実施する
- 顧客への告知・広告活動を行う
人員計画を策定する
閑散期のうちに繁忙期に必要となる人員の採用・配置計画を策定しましょう。
まず過去の繁忙期のデータをもとに、次回必要となる人員数と求めるスキルを明確にします。必要に応じて、短期人材派遣やスポット・短期アルバイトの採用を検討し、採用計画を策定しましょう。
閑散期のうちに繁忙期の人材確保・採用活動を行うことで、求めるスキルを設定する精度が高まるほか、採用後の教育時間も確保しやすくなります。
また、繁忙期までに従業員のスキルアップを図るために、既存従業員の教育計画を策定しておくことも大切です。
業務プロセスを見直す
閑散期の間に業務プロセスを見直しておくことも大切です。
過去の繁忙期のワークフローを以下のプロセスで見直してみましょう。
- 現状の業務フローを可視化し、非効率な部分を特定する
- 特定した課題をもとに、業務フローを再設計(ITツールなどを活用した効率的なワークフローを構築)
- 必要に応じてマニュアルの更新・作成を行う
繁忙期には業務のスピードアップが求められます。業務円滑化のために最新の業務マニュアルを整備しておくことも、繁忙期の混乱を最小限に抑えるポイントです。
なお業務プロセスを再設計する際には、従業員から改善提案を募集し、現場の声を反映した動きやすいフローにすることが大切です。
在庫管理体制を整備する
小売業・販売業の場合は、繁忙期を迎える前に在庫管理体制を構築・整備しておきましょう。
適切な在庫を確保するためには、売上の予測が必要です。売上や顧客数の変動などのデータを分析し、需要を予測して仕入れ量を確定しましょう。過去の売上データにおいて、特定の月に需要が伸びる傾向がある場合は、その時期に向けて準備を前倒しで始められます。
併せてサプライチェーンを見直し、納期を短縮できないかも検討します。
また、ストックを確保すると同時にストックする場所の確保も必要です。セールなどの大量仕入れがある場合は、臨時のストックスペースが必要となる場合があるので、迅速に確認し手配しましょう。
システム・ツールの導入・整備を行う
閑散期のうちにシステム・ツールの導入と整備を済ませておくことも、繁忙期をスムーズに乗り越えるポイントです。
ITツールの導入により、定型業務を自動化できれば、繁忙期の業務負担の軽減につながります。業務課題に応じて業務管理ツールやRPA、コミュニケーションツールの導入を検討・導入しましょう。
併せて既存のシステムに対しても、繁忙期に対応できるだけのシステム容量を確保しておきます。繁忙期にシステムトラブルで業務がストップしないよう、閑散期のうちにメンテナンスしておくことが大切です。
従業員トレーニングを実施する
閑散期の間に新規採用者や既存社員の研修も実施しておきましょう。
従業員が繁忙期の忙しさに打ち勝てるために、時間管理やストレスマネジメントのスキルを習得させることをおすすめします。また、新しいITツールを導入する場合は、ツールの使用方法や業務プロセスの変更カ所の周知も必要です。
また、繁忙期の柔軟な人材配置を想定し、既存従業員のクロストレーニングも実施するとよいでしょう。各従業員が業務の全工程を俯瞰でき、自ら効率的に動けるようになります。繁忙期の実務をシミュレーションしておくとさらに安心です。
なお、閑散期には短期的な繁忙期対策に加え、以下のような長期的成長を促す人材育成の実施もおすすめです。
- 継続的な改善を促す意識の醸成
- 円滑な人間関係の構築およびチームビルディング
顧客への告知・広告活動を行う
小売業・販売業などのキャンペーンの実施前には、顧客への告知・広告活動を行う必要があります。
キャンペーン前に行うべき準備としては、情報発信や顧客へのキャンペーン告知、ポイントカード・クーポンの配布などの集客活動が挙げられます。X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSを使えば、高額な広告費用をかけずに拡散力が高くターゲットを絞った広告を出すことが可能です。
なお、広告の運用には手間がかかりノウハウも必要となるため、自社で運用経験のない場合は、広告運用を代行会社に委託するとよいでしょう。
繁忙期後に行うべき今後に向けた対策

無事に繁忙期を乗り切った後にもやるべきことがあります。ここでは次回以降の繁忙期に向けた対策を解説します。
- 次回につなげる振り返りを行う
- スタッフのケアにも留意する
次回につなげる振り返りを行う
繁忙期の後には、次回につなげる振り返りを行うことが大切です。
振り返りの目的は、次回以降改善できるようPDCAをスピーディーに回すことです。繁忙期を乗り切った後、最終的な「成功・不成功」にしか目を向けなければ、次回に活かす改善ポイントが曖昧になってしまいます。
しかし、振り返りを行えば「どの点が良かったのか」「次回にどう活かせるのか」を明確にできます。繁忙期の振り返りを次回につながる有意義なものにするには、以下のフレームワークを使うことがおすすめです。
フレームワーク
概要
KPT法
- Keep:成果が出たこと(今後継続すること)
- Problem:発生した課題(直したいこと)
- Try:改善したいこと
YWT法
- Y(やったこと):成長への挑戦
- W(わかったこと):気づきや学び
- T(次にやること):発見を活かし次の計画・行動に反映
Star fish法
- Keep Doing:すでに効果が出ており、今後も続けたいこと
- More of:すでに実践し効果が大きく、さらに注力したい
- Less of:実践しているが効果が薄い
- Stop Doing:メリットがなく廃止すべきこと
- Start Doing:次回実践したいこと
World Cafe法
カフェのようなくつろいだ雰囲気の中で自由にアイデアを出し合う
TimeLine法
メンバー全員の出来事を付箋で時系列に並べ、良かったこと・悪かったことを分析する
振り返りをもとにPDCAを回し、次回の繁忙期に向けた改善施策を実施しましょう。
スタッフのケアにも留意する
繁忙期は忙しく業務に追われていたので、終了後はスタッフのケアも大切です。
長時間勤務や休日出勤、不規則なシフトが続くと、繁忙期が終わって気が緩んだ途端に体調を崩す恐れがあります。
また、体調以外に達成感を味わった後の「燃え尽き症候群」にも注意が必要です。一般に繁忙期はテンションを上げて臨んでいるケースが多く、やり切ったことでバーンアウトしやすいのです。
しかし本来は繁忙期の販促活動後にはアフターフォローなど、やるべきことは多数あるため、なるべく早期に通常の業務体制に戻さなければなりません。
まずはスタッフの疲労度合いをチェックし、労いの声掛けを行うとともに、適宜シフト調整を行いましょう。精神的な燃え尽き症候群に対しては、本人の体調に問題がなければ、新しい目標を立てるよう促すことも一つの方法です。
繁忙期の対策は業務効率化と人員調整がカギを握る

繁忙期に生じる課題への対策は、閑散期における事前の準備が大きなウエイトを占めます。
特に業務プロセスの効率化や適切な人員調整が、繁忙期の業務を円滑化するカギを握るといっても過言ではありません。具体的な対策としては、ITツールの導入や短期雇用・アウトソーシングなどが挙げられます。
繁忙期の業務効率化にはアウトソーシングがおすすめです。
Fammアシスタントオンラインでは、各分野のハイスキルな人材がバックオフィス業務からSNS・広告運用まで、多彩な業務に対応しています。初月40,000円で利用できるキャンペーンも実施しているので、繁忙期をスムーズに乗り越えたい方は、ぜひご相談ください。
\ 月額¥60,000~利用できる /
資料「Fammアシスタントオンラインサービス」
を無料ダウンロード

