業務の属人化解消とは|原因・リスク・具体的な解消方法と成功事例を徹底解説
-
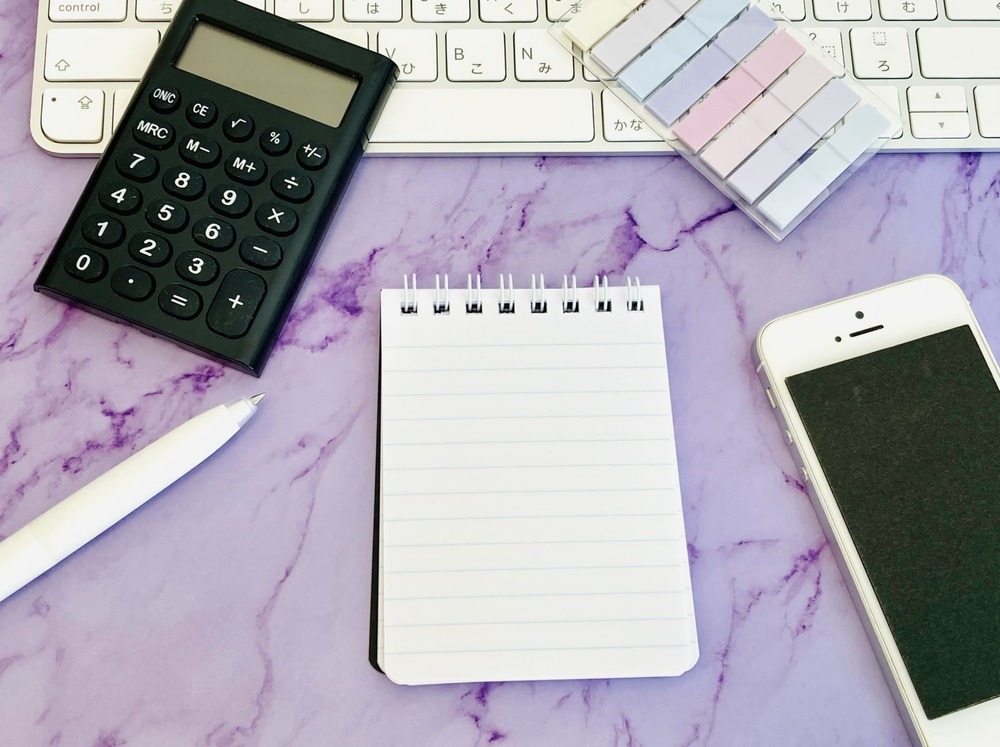
-
業務の属人化とは、特定の人しか業務を把握していない状態のことです。
近年、働き方改革やリモートワークの普及により、業務の属人化解消が多くの企業の課題となっています。
属人化した業務は、担当者の不在時や退職時に業務が停滞するリスクがあり、企業の成長を妨げる要因になりかねません。
本記事では、業務の属人化の意味から原因、弊害やリスク、そして具体的な解消方法まで、総務・人事担当者が知っておくべき情報を網羅的に解説します。
業務の属人化に悩む担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
この記事でわかること
- 業務の属人化が起こる原因とリスクが理解できる
- 効果的な属人化解消方法がわかる
- 属人化を解消するならFammアシスタントオンラインがおすすめ
\ 月額¥60,000~利用できる /
資料「Fammアシスタントオンラインサービス」
を無料ダウンロード目次
業務の属人化とは

業務の属人化とは、特定の人だけが業務内容や進め方を把握している状態を指します。
具体的には、ある業務の手順やノウハウ、進捗状況などを特定の担当者しか理解していない状況です。
このような状態では、担当者が不在の際に業務が停滞したり、退職時に引き継ぎが困難になったりするリスクが生じます。
近年、働き方改革やリモートワークの普及により、業務の属人化解消が多くの企業の課題となっています。
属人化した業務は企業の成長を妨げる要因となるため、組織的な対策が求められています。
属人化の対義語は「標準化」であり、業務を可視化して誰でも遂行できる状態にすることが重要です。
属人化とブラックボックス化の違い
業務における属人化とブラックボックス化は、どちらも組織運営に悪影響を及ぼす状態ですが、その性質には違いがあります。
属人化は、特定の担当者しか業務プロセスやノウハウを理解していない状態です。
担当者が不在になると業務が滞る、あるいは品質が低下するリスクがあります。
しかし、属人化している業務でも、担当者はその業務について一定の理解を持っている点が特徴です。
一方、ブラックボックス化は、業務のプロセスや内容が誰にも理解できない状態です。
なぜその業務が必要なのか、どのように行われているのかが不明確で、改善や効率化が困難になります。
属人化が進んだ結果、業務がブラックボックス化するケースも少なくありません。
例えば、長年同じ担当者が行ってきた業務が、手順書やマニュアルもなく、他の人が内容を把握できないままになっている場合、それはブラックボックス化していると言えます。
属人化
ブラックボックス化
内容
特定の人だけが業務内容や進め方を把握している状態
業務の実態が外部からまったく見えない状態
特徴
担当者不在時に業務が停滞する
業務の中身が完全に不透明になる
リスク
人材流出時の業務継続性の低下
不正やミスの発見が困難になる
属人化とスペシャリストの違い
属人化とスペシャリストは、どちらも特定の人物が業務を深く理解している状態を指しますが、組織への影響や知識の共有において大きな違いがあります。
属人化は、その担当者しか業務を遂行できない状態であり、知識やスキルが組織内で共有されにくい傾向があります。
担当者が不在になると業務が滞り、組織全体の生産性低下を招く可能性があるのが属人化です。
一方、スペシャリストは、特定の分野で高度な専門知識やスキルを持つ人材であり、その知識を組織に還元し、全体のレベルアップに貢献します。
スペシャリストは、自らの知識や経験を積極的に共有し、他のメンバーの育成にも尽力できます。
属人化
スペシャリスト
内容
業務やノウハウが特定の個人に依存している状態
特定分野で高度な専門知識・技術を持つ人材
専門性
必ずしも高い専門性を必要としない
高度な専門性を持つ
情報共有
知識やノウハウが共有されない傾向
積極的に知識を共有し、他者を育成する
組織への影響
業務の停滞リスクや非効率化をもたらす
組織の成長や問題解決に貢献する
暗黙知と形式知とは
暗黙知と形式知は、知識の性質を分類する重要な概念です。
暗黙知とは、個人の経験や勘、直感に基づく知識であり、言語化や数値化が難しいものを指します。
例えば、職人の技術や営業担当者の話術などは暗黙知に該当します。
一方、形式知は言語や図表、数値で明確に表現された知識であり、マニュアルや業務フローなどがその例です。
両者の違いは、共有可能性と客観性にあります。
暗黙知は個人に依存しやすく、属人化のリスクを伴いますが、形式知は誰でも理解・共有できるため、組織全体で活用可能です。
暗黙知
形式知
内容
言語化されていない知識
言語化・可視化された知識
特徴
他者に伝えにくい
共有しやすい
例
経験や勘に基づく判断
マニュアルや手順書
業務が属人化する5つの主要な原因
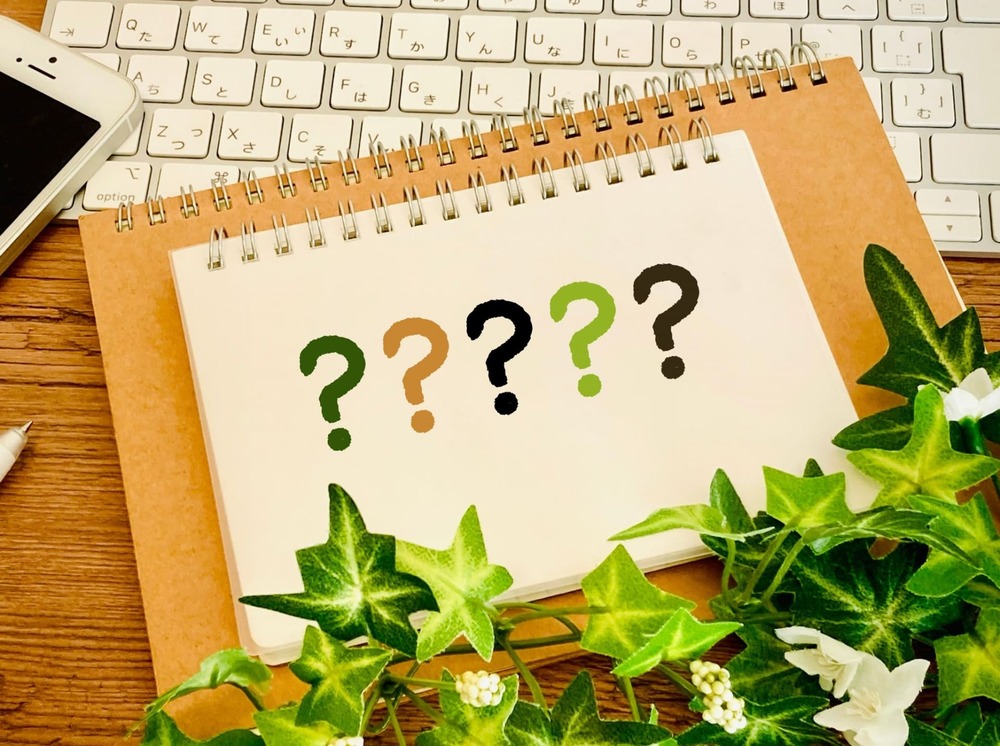
業務の属人化は多くの企業が直面する課題です。
なぜ業務の属人化が進行してしまうのでしょうか。
以下では、業務が属人化する5つの主要な原因について詳しく解説します。
- マニュアルの未整備による口頭での引き継ぎ
- 専門性の高い業務は特定の人に集中しやすい
- 従業員の標準化への消極的な姿勢
- 情報共有を促す仕組みの不足
- リモートワークによる情報共有の減少
マニュアルの未整備による口頭での引き継ぎ
業務の属人化が進む最も一般的な原因は、マニュアルの未整備です。
多くの企業では、業務手順やノウハウを文書化せず、口頭での引き継ぎに依存しています。口頭での伝達は情報の抜け漏れが生じやすく、伝える側の記憶や解釈に左右されるため、正確な情報共有が困難です。
たとえマニュアルが存在していても、形骸化していたり、最新情報に更新されていなかったりすれば、実質的に機能していません。
このような状況では、担当者が独自の方法で業務を進めるようになり、その知識は個人に蓄積されていきます。
結果として、担当者不在時には業務が停滞し、退職時には貴重なノウハウが失われるリスクが高まります。
マニュアルは「業務共有のための教科書」であり、その整備は属人化防止の第一歩です。
専門性の高い業務は特定の人に集中しやすい
専門性の高い業務は、特定のスキルや知識が求められるため、特定の担当者に集中しやすい傾向があります。
例えば、製造業における特殊な技術や、IT分野でのプログラミングスキルなどは、その業務を遂行できる人材が限られるため、属人化が進む原因です。
また、こうした業務は学習や習得に時間がかかる場合が多く、新たな人材の育成が後回しになることで、さらに依存度が高まります。
さらに、専門性の高い業務では担当者自身が「自分しかできない」と意識を持ちやすく、他者への引き継ぎや共有が進みにくいことも問題です。
このような状況では、担当者の不在時に業務が停滞するリスクが高まり、組織全体の生産性や柔軟性に悪影響を及ぼします。
専門性の高い業務の属人化を防ぐには、複数人での担当制や段階的な知識共有を進め、特定の個人に依存しない体制づくりが重要です。
従業員の標準化への消極的な姿勢
業務の属人化が進む原因として、従業員が業務の標準化に消極的な姿勢を示すことが挙げられます。
これは、自身のスキルや知識が組織内で唯一のものであると優位性を保ちたい、あるいは変化に対する抵抗感などが考えられます。
例えば、「この業務は自分にしかできない」と意識が強い従業員は、マニュアル作成や情報共有への姿勢が消極的です。
このような状況では、組織全体の生産性低下や担当者不在時の業務停滞を招く可能性があります。
属人化を防ぐためには、従業員に標準化のメリットを理解してもらうことが重要です。
例えば、業務プロセスを可視化し、効率化による負担軽減や組織全体での情報共有の利点を具体的に示すことで、抵抗感を和らげられます。
情報共有を促す仕組みの不足
多くの企業では、日常業務の中で発生する知識やノウハウを効果的に共有するための体制が整っていません。
例えば、グループウェアやチャットツールなどのコミュニケーションツールが未導入だったり、導入していても十分に活用されていなかったりする状況です。
また、情報共有のためのワークフローが機能していない場合、情報の伝達に多くの工数がかかり、業務過多の状態では情報共有まで手が回らなくなります。
さらに、情報共有を促進する組織文化や評価制度が整備されていないことも大きな要因です。
積極的に知識を共有した社員が適切に評価されなければ、情報共有のモチベーションは低下します。
情報共有ツールの導入やワークフローの整備だけでなく、「情報共有を積極的に行う従業員を評価する制度」や「共有文化の醸成」が重要です。
リモートワークによる情報共有の減少
オフィスで対面勤務をしていた頃は、同僚との何気ない会話や相談を通じて自然と情報共有が行われていましたが、リモート環境ではこうした偶発的なコミュニケーションの機会が大幅に減少します。
例えば、オフィスであれば「ちょっと相談して良い?」と気軽に声をかけられる状況が、リモートでは「会議を設定する」「チャットで連絡する」といった明示的なアクションが必要です。
リモート環境ではこうした機会が失われ、意図的に情報共有の場を設けない限り、各自が孤立して業務を進める状況が生まれます。
また、リモートワークでは相手の業務状況が見えにくいため、「忙しそうだから後にしよう」と判断して結局共有されないケースも深刻です。
こうした状況が続くと、各自が独自の方法で業務を進めるようになり、知識やノウハウが個人に蓄積され、組織全体での共有が進まなくなります。
この問題を解決するためには、定期的なオンラインミーティングや出社日を設けることが重要です。
業務の属人化がもたらす7つの弊害とリスク
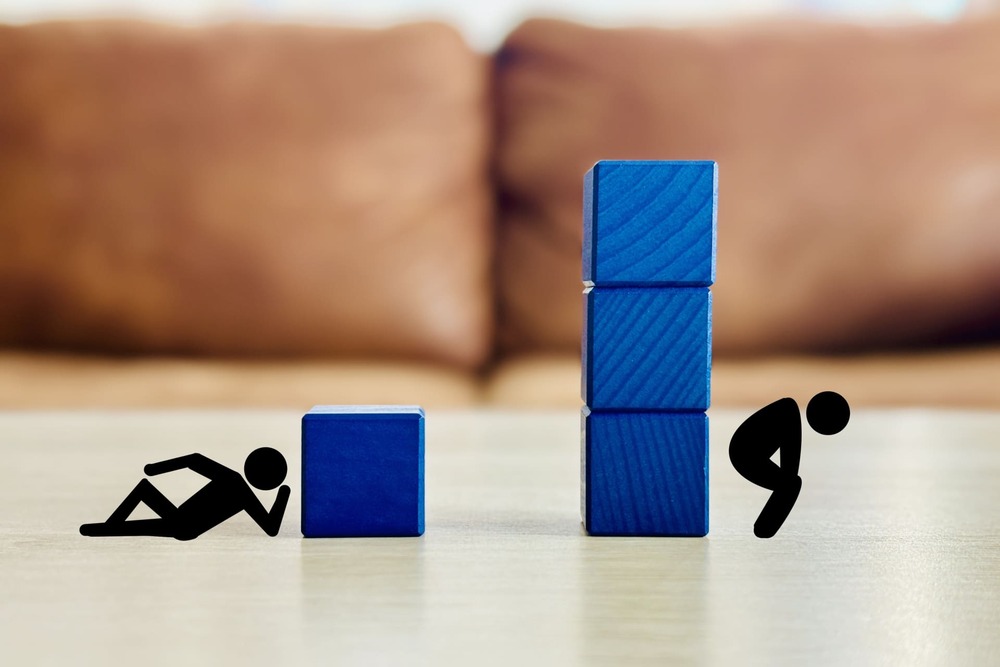
業務の属人化は、組織にとってさまざまなリスクやデメリットをもたらします。
ここでは、属人化によって生じる7つの主な弊害とリスクについて解説します。
以下のリスクを認識し、適切な対策を講じることで、組織全体の生産性向上と安定した成長を目指しましょう。
- 長時間労働によって業務効率が低下する
- 業務内容が不透明であるため管理が困難になる
- ミスやトラブルが発見しにくくなる
- 退職・異動時に引き継ぎが困難になる
- 工数管理や適正評価がしづらくなる
- 担当者によってサービス品質にばらつきが生じる
- 組織としての成長が妨げられる
長時間労働によって業務効率が低下する
属人化が進むと特定の担当者に業務が集中し、長時間労働が発生しやすくなるリスクがあります。
担当者は業務を抱え込み、抱えている業務量や業務の進捗状況を共有しないため、周囲はサポートできない状況になるためです。
その結果、担当者の負担が増大し、疲弊してしまいます。
長時間労働は、担当者の集中力や判断力を低下させ、ミスや手戻りの増加にもつながります
組織全体の生産性低下を招くため、業務の属人化は解消しなければなりません。
業務内容が不透明であるため管理が困難になる
業務が属人化すると、担当者以外には業務内容や進捗状況が見えにくくなり、管理が困難になります。
上司やチームリーダーは、担当者が「何をしているのか」「どのように進めているのか」「どれくらいの時間がかかっているのか」を把握できません。
その結果、担当者の業務量や成果を適正に評価できず、人事評価や人員配置の判断を誤る可能性があります。
また、業務の重複や非効率な手順に気づきにくくなり、改善の機会を逃してしまいます。
業務の透明性を高めるには、タスク管理ツールや進捗管理システムを導入し、各担当者の業務内容や進捗状況を可視化することが重要です。
ミスやトラブルが発見しにくくなる
業務の属人化が進むと、業務内容を理解している人が限られるため、ミスやトラブルの発見が困難になります。
通常、複数の目で確認することでミスは発見されやすくなりますが、属人化した業務ではそのチェック機能が働きません。
例えば、ある担当者がExcelのマクロを組んでデータ分析を行っている場合、そのマクロのロジックを理解しているのがその担当者だけだと、誤った集計が行われていても誰も気づかない可能性があります。
また、他の従業員が業務内容を理解していないため、ミスが発覚する可能性が低く、担当者が個人的な評価を気にしてミスを隠してしまう恐れもあります。
退職・異動時に引き継ぎが困難になる
属人化すると担当者の退職や異動時に深刻な問題が発生します。
特定の個人だけが業務の詳細を把握している状態では、その知識やノウハウを短期間で次の担当者に引き継ぐことが困難になるためです。
例えば、長年同じ業務を担当してきた社員が突然退職を申し出た場合、数週間の引継ぎ期間では膨大な暗黙知を伝えきれません。
また、属人化した業務では「何を引き継ぐべきか」自体が不明確なため、重要な情報が抜け落ちるリスクも高まります。
このような状況は、業務の停滞だけでなく、顧客対応の遅れやサービス品質の低下など、企業全体の信頼性にも悪影響を及ぼしかねません。
工数管理や適正評価がしづらくなる
属人化は、特定の担当者しか業務内容を把握していないため、上司や管理者は「どのくらいの時間がかかるべき業務なのか」「どの程度の難易度なのか」を正確に判断できません。
例えば、データ分析業務が属人化している場合、担当者が「この分析には3日かかります」と言えば、それが適切な工数なのか過大なのか判断する基準がありません。
また、業務の成果についても、専門知識がなければ品質を評価することは難しいでしょう。
このような状況では、人事評価や業務配分の適正化が妨げられ、組織全体の生産性向上を阻害します。
さらに、担当者自身も自分の業務の価値を客観的に示せないため、適切な評価を受けられない可能性があります。
工数管理と適正評価の透明性を確保するためには、業務の可視化と標準化が不可欠です。
担当者によってサービス品質にばらつきが生じる
業務が属人化すると、担当者ごとに業務の進め方や顧客対応が異なり、サービス品質にばらつきが生じます。
例えば、ベテラン社員が独自のノウハウを活用して高品質な対応を行う一方で、経験の浅い社員が同じ業務を担当すると品質が低下する可能性があります。
このような状況は、。顧客から「以前は対応が良かったのに今回は違う」といった不満やクレームにつながりかねません
さらに、業務手順書やマニュアルが整備されていない場合、標準的な進め方が共有されず、担当者の経験や判断に依存するため、品質の安定性を確保することが難しくなります。
このような属人化による品質のばらつきは、顧客満足度の低下や企業の信頼性に悪影響を与えかねません。
組織としての成長が妨げられる
属人化は、組織全体の成長を阻害する深刻な問題です。
特定の個人に知識やノウハウが集中すると、それらが組織の共有財産として蓄積されず、組織としての学習や進化が妨げられるためです。
例えば、顧客対応のノウハウが一部の社員に限定されていると、その知見を基にした新たなサービス開発や業務改善のアイデアが生まれにくくなります。
また、過去の成功事例や失敗事例が共有されないため、同じ失敗を繰り返したり、成功体験を拡大できなかったりする状況になりかねません。
さらに、属人化した環境では新しい視点や改善提案が取り入れられにくく、イノベーションが起こりにくい保守的な組織文化が形成されがちです。
結果として、市場環境の変化に対応できず、競争力の低下を招くリスクがあります。
組織の持続的な成長のためには、個人の知識を組織の知恵へと変換する仕組みづくりが不可欠です。
業務の属人化解消によるメリット

業務の属人化を解消すると、組織にはさまざまなメリットが生まれます。
ここでは、業務効率と生産性の向上から変化への対応力強化まで、属人化解消がもたらす5つのメリットを解説します。
これらのメリットを理解し、属人化解消に積極的に取り組むことで、組織全体の成長を加速させましょう。
- 業務効率と生産性の向上
- 組織的なナレッジ・ノウハウの蓄積
- サービス品質の安定化と向上
- テレワーク環境への適応力強化
- 人材流動化への対応力向上
業務効率と生産性の向上
属人化された業務では、特定の担当者に負担が集中し、非効率な作業や長時間労働が常態化しやすい状況です。
しかし、業務を標準化し、複数人で共有できる体制を整えることで、業務負担を分散し、作業のスピードと質を向上させることが可能です。
例えば、マニュアルやナレッジマネジメントシステムを活用して業務手順を明確化すれば、新しい担当者でもスムーズに業務に取り組めます。
また、情報共有が促進されることで、従業員同士の連携が強化され、無駄な作業や重複した作業が削減できます。
組織的なナレッジ・ノウハウの蓄積
業務の属人化を解消するには、個人に蓄積されていた知識やノウハウが組織全体の財産となります。
属人化された環境では、熟練社員が培ってきた経験やスキルは退職と同時に失われてしまいますが、標準化によってそれらの知識を形式知として残すことが可能です。
例えば、顧客対応の秘訣や業務上のトラブル対処法など、長年の経験から得た暗黙知を文書化することで、新入社員でも短期間で一定レベルのスキルを習得できます。
また、複数の社員が同じ業務に携わることで、それぞれの視点からの改善提案が生まれ、業務プロセス自体が進化します。
サービス品質の安定化と向上
属人化の解消は、サービス品質を安定させ、向上させることが可能です。
属人化した業務では、担当者によって対応方法や業務スキルが異なるため、サービス品質にばらつきが生じます。
例えば、顧客対応業務が属人化していると、ベテラン担当者の対応は迅速かつ的確である一方、経験の浅い担当者の対応は遅れがちになるといった不均衡が生じます。
このような状況は顧客満足度の低下につながりかねません。
業務の標準化を進めることで、誰が担当しても一定の品質を保つことが可能です。
具体的には、業務フローやマニュアルを整備し、従業員全員が統一された手順で業務を遂行できる環境を構築します。
これにより、ミスや抜け漏れを防ぎ、サービスの一貫性が確保され、安定した品質のサービスを提供できます。
テレワーク環境への適応力強化
テレワーク環境では、従業員が物理的に離れた場所で働くため、情報共有やコミュニケーションが不足しやすくなります。
この状況は、業務の属人化を助長し、組織全体の効率や生産性に悪影響を及ぼす可能性があります。
しかし、属人化を解消し、業務を標準化すると、テレワーク環境への適応力を強化することが可能です。
例えば、業務手順書やマニュアルを整備し、クラウドベースのナレッジマネジメントシステムを活用すると、従業員間での情報共有が円滑になります。
担当者不在時でも他のメンバーが業務を代行できる体制が整い、リモートワーク中でも安定した業務運営が可能です。
さらに、進捗状況やタスク内容をリアルタイムで共有できるツールを導入することで、チーム間の連携がより強化できます。
人材流動化への対応力向上
近年、終身雇用の減少や働き方の多様化により、転職や部署異動、副業・兼業など人材の流動性が高まっています。
このような環境下では、特定の個人に依存した業務体制は大きなリスクです。
業務の標準化を進めることで、新しい人材がスムーズに業務に参加できるようになり、既存社員の異動や退職時の引継ぎも円滑に行えます。
例えば、マニュアルやナレッジベースが整備されていれば、新入社員の教育期間を短縮でき、早期戦力化が可能です。
また、社内での人材の適材適所への配置も柔軟に行えるようになり、組織全体の生産性向上につながります。
業務の属人化を解消する5つの効果的な方法

業務の属人化を解消するためには、以下の5つの方法が効果的です。
- 業務のマニュアル化と標準化を進める
- 業務責任と権限を適切に分散する
- 従業員の意識改革と組織文化の醸成を行う
- ITツールを活用する
- アウトソーシング活用する
それぞれの方法について詳しく解説します。
業務のマニュアル化と標準化を進める
属人化解消の最も効果的な方法は、業務のマニュアル化と標準化です。
まず、現状の業務フローを可視化し、各タスクの手順や注意点を明確にします。
次に、それらを誰が見てもわかるようにマニュアルとして文書化します。
効果的なマニュアルには、業務の目的、具体的な手順、発生しやすいトラブルとその対処法、必要な資料やツールなどを含めましょう。
特に重要なのは、暗黙知を形式知に変換する視点です。
「なぜそうするのか」といった理由や「こうすると効率が上がる」といったコツも記載すると、単なる手順書以上の価値を持ちます。
マニュアル作成後は定期的な見直しと更新を実施しましょう。
業務環境や条件が変化しても最新の内容を維持することで、マニュアルの形骸化を防ぎ、継続的な業務標準化を実現できます。
業務責任と権限を適切に分散する
業務の属人化解消には、特定の個人に集中している責任と権限を適切に分散することが効果的です。
一人の社員に業務が集中すると、その人の不在時に業務が停滞するだけでなく、不正リスクも高まります。
まず、現状の業務フローを可視化し、特定の個人に権限が集中している箇所を特定します。
次に、業務の性質に応じて複数人での担当制を導入したり、申請者と承認者を分けるなどの相互牽制の仕組みを構築しましょう。
例えば、経理業務では伝票起票と承認を別の担当者が行うことで、チェック機能が働き不正防止にもつながります。
従業員の意識改革と組織文化の醸成を行う
属人化が進む背景には「自分の地位を守りたい」「専門性を認めてもらいたい」といった従業員の心理があります。
この意識を変えるには、まず経営層が属人化のリスクを明確に伝え、情報共有の重要性を浸透させることから始めましょう。
効果的な意識改革には、従業員参加型のワークショップを開催し、業務の課題や改善策を自ら考える機会を設けることが有効です。
また、情報共有や業務の標準化に貢献した従業員を評価する制度を導入すれば、積極的な行動変容を促せます。
組織文化の醸成においては、「失敗を許容する環境づくり」が重要です。
チャレンジを称える表彰制度を設けるなど、新しい取り組みを奨励する風土を作ることで、従業員が自発的に業務改善や知識共有に取り組む文化が根付きます。
経営層が率先して行動し、継続的なコミュニケーションを通じて、全員が当事者意識をもって業務に取り組む組織へと変革させましょう。
ITツールを活用する
業務の属人化解消には、適切なITツールの活用が効果的です。
特に、情報共有やナレッジマネジメントに特化したツールは、暗黙知を形式知に変換し、組織全体で共有する基盤となるため効果的です。
例えば、ワークフローシステムを導入すれば、業務の流れを可視化し、誰が何をどのように進めるべきかを明確にできます。
また、ナレッジマネジメントシステムは、業務マニュアルや過去の事例、ノウハウなどを一元管理し、必要な時に必要な情報にアクセスできる環境が整います。
さらに、チャットツールやグループウェアなどのコミュニケーションツールは、リモートワーク環境でも円滑な情報共有が可能です。
タスク管理ツールを活用すれば、業務の進捗状況を可視化でき、特定の担当者に依存せずに全体の状況を把握できます。
ITツールの導入は初期コストがかかるものの、長期的には業務効率の向上や属人化リスクの低減など、大きなリターンが期待できます。
アウトソーシング活用する
業務の属人化を解消する効果的な方法の一つに、アウトソーシングの活用があります。
アウトソーシングとは、特定の業務を外部の専門会社に委託することで、社内リソースをコア業務に集中させる仕組みです。
アウトソーシングは、属人化が進んだ業務や専門性が求められる業務に特に有効です。
例えば、給与計算やコールセンター業務など、定型的かつ負担が大きい業務をアウトソーシングすれば、社内の人的リソースを重要な戦略業務に振り向けることが可能です。
また、専門知識が必要なITシステム運用やマーケティング業務を委託することで、品質向上と効率化を同時に実現できます。
さらに、アウトソーシングは、必要な時だけ外部に委託すると、固定費を変動費化や無駄なリソースを削減できるなど、コスト削減にも貢献します。
業務の属人化解消に成功した企業事例3選

ここでは、業務の属人化解消に成功した企業の事例を3つ紹介します。
これらの事例から、属人化解消に向けた具体的な取り組みや、その効果を把握し、自社での取り組みの参考にしてください。
- 株式会社トプコン:開発業務の属人化を解消し工数を約1/5に短縮
- ドリコ株式会社:ナレッジマネジメントシステムで技術継承の基盤を構築
- 株式会社マルイ:AIを活用した工数削減と属人化解消を実現
株式会社トプコン:開発業務の属人化を解消し工数を約1/5に短縮
株式会社トプコンは、「医(ヘルスケア)・食(農業)・住(建設)」の分野でDXを推進する企業です。
同社では、以前利用していたワークフローシステムがモバイル未対応なため、申請承認業務の停滞や保守運用の工数増加、プログラミングが必要な箇所が多く、開発業務が属人化しているといった課題がありました。
そこで、誰にでも使いやすいUIで内製化しやすい点を評価し、ワークフローシステム「AgileWorks」を導入しました。
開発業務などの属人化を防ぐ体制構築にも力を注ぎ、新たに加わったメンバーでも開発業務を行えるよう実現しています。
従来1件につき40時間を要していたワークフローの開発が8時間程度まで短縮に成功しています。
ドリコ株式会社:ナレッジマネジメントシステムで技術継承の基盤を構築
資源開発事業や水環境事業を展開するドリコ株式会社では、紙文化が強く根付いており、社内のほとんどの業務が紙の帳票とアナログな入力業務で組み立てられていました。
そんな紙ベースの帳票運用は、多くの手間が発生するだけでなく、帳票の紛失や入力ミスといったリスクも課題となっていました。
そこで、同社はワークフローシステム「X-point Cloud」を導入しました。
70種類ほど存在していた紙の帳票をほぼすべてデジタル化し、申請書作成にかかる手間を削減し、入力ミスなどのリスク低減を実現しています。
また、過去のデータが「X-point Cloud」上に蓄積され、簡単に閲覧・参照できる仕組みが整ったことで、若手従業員への知識・技術の継承にも役立てられています。
株式会社マルイ:AIを活用した工数削減と属人化解消を実現
岡山県、鳥取県、島根県でスーパーマーケット事業を展開している株式会社マルイは、発注業務における属人化に課題を抱えていました。
そこで同社は、AIを活用した需要予測システムを導入し、発注業務における工数削減と属人化解消を実現しました。
具体的には、販売実績やキャンペーン情報、気象データをインプットして学習させたAIを用いて、野菜や水産物の需要を予測しました。
この取り組みにより、発注時間が50%削減され、従来の経験や勘に頼っていた発注業務の属人化の解消に成功しています。
また、AIによる需要予測は、客数予測精度の向上や廃棄ロスの削減にも寄与し、店舗の業務効率化とサービス品質向上にも役立っています。
属人化解消を進める際に気をつけるべきポイント

業務の属人化解消は一度の取り組みで完結するものではなく、継続的な改善が必要です。せっかく標準化した業務も、時間の経過とともに新たな属人化が生じる可能性があります。
以下では、属人化解消を進める際に気をつけるべきポイントを紹介します。
- 業務を可視化し属人化している箇所を特定する
- コミュニケーションと情報共有の場を設ける
- 継続的な改善や定期的な見直しを行う
- マニュアルの定期的な更新と形骸化を防止する
業務を可視化し属人化している箇所を特定する
属人化解消の第一歩は、業務の可視化から始まります。
まず、業務プロセスをフローチャート形式で描き出し、全体の流れを把握しましょう。
次に、各作業ステップを「その作業を代行できるか」といった観点でチェックします。
代行が難しい作業が属人化している箇所です。
この特定作業では、業務の一連の流れで発生する作業や関係する部署、やり取りされる情報を洗い出し、図式化することが重要です。
また、業務の詳細を把握するために、担当者へのヒアリングも欠かせません。
「どのような業務があり、どれくらいの時間がかかるか」「難易度や重要度はどの程度か」「必要なスキルは何か」といった点を明確にしましょう。
可視化された業務フローを分析することで、ボトルネックや非効率な手順を発見でき、効果的な改善策の立案につながります。
コミュニケーションと情報共有の場を設ける
属人化を解消するためには、コミュニケーションと情報共有の場を設けることが重要です。情報共有が不足すると業務の透明性が失われ、特定の担当者に業務が集中する属人化が進みやすくなります。
これを防ぐためには、従業員同士が積極的に情報を交換し合える環境を整えましょう。
具体的な取り組みとしては、以下のような方法があります。
- 定期的なミーティングや報告会の開催
- 社内SNSやチャットツールの活用
- 部署間交流やイベントの実施
これらの場を設けることで、従業員間で業務内容や進捗状況を共有しやすくなり、属人化のリスクを軽減できます。
継続的な改善や定期的な見直しを行う
業務の属人化解消は一度の取り組みで完結するものではなく、継続的な改善活動として位置づけることが重要です。
標準化された業務プロセスやマニュアルも時間の経過とともに現場の実態とのズレが生じたり、業務環境の変化により陳腐化したりする可能性があります。
属人化解消を持続させるためには、定期的な見直しの機会を設けましょう。
例えば、四半期ごとにマニュアルの内容を検証し、実際の業務との乖離がないか確認します。
また、業務改善の提案を従業員から募り、より効率的な方法があれば積極的に取り入れる姿勢も大切です。
PDCAサイクルを回し続けることで、新たな属人化の芽を早期に発見し、対処できます。
特に組織変更や新システム導入など、業務環境が大きく変わる際には、必ず標準化された業務の見直しを行い、属人化が再発しないよう注意を払いましょう。
業務の属人化を解消して持続的な組織成長を実現しよう

業務の属人化は、特定の社員だけが業務を把握している状態であり、組織の成長を妨げる大きな課題です。
属人化が進むと、長時間労働や業務の停滞、サービス品質のばらつき、ナレッジの蓄積不足など、さまざまな弊害が生じます。
属人化解消の取り組みを継続的に行うことで、人材の流動化やテレワーク環境にも柔軟に対応できる強固な組織基盤を構築できます。
業務の可視化や情報共有の仕組みづくりを進め、特定の個人に依存しない組織づくりを目指しましょう。
業務の属人化解消をサポートするなら、『Fammアシスタントオンライン』がおすすめです。
専任のアシスタントが業務の標準化やマニュアル作成を支援し、属人化している業務を効率的に可視化します。
属人化に悩む企業はぜひ導入をご検討ください。
\ 月額¥60,000~利用できる /
資料「Fammアシスタントオンラインサービス」
を無料ダウンロード

