人件費は固定費?変動費?分類方法やメリット、削減方法を徹底解説
-

-
企業の財務管理において、人件費の適切な分類は重要な課題です。
しかし、人件費を固定費と変動費のどちらに分類すべきか迷っている企業担当者も多いのではないでしょうか。
人件費は一般的に固定費として扱われますが、業種や雇用形態によっては変動費として調整することも可能です。
本記事では、固定費と変動費の基本的な違い、人件費を変動費化するメリット・デメリット、人件費を最適化する方法を解説します。
コスト削減や経営の柔軟性向上を目指す企業担当者は、ぜひ最後までご覧ください。
この記事でわかること
- 固定費と変動費の違い
- 人件費を固定費から変動費に変えるメリット・デメリット
- アウトソーシングを活用するならFammアシスタントオンラインがおすすめ
\ 月額¥60,000~利用できる /
資料「Fammアシスタントオンラインサービス」
を無料ダウンロード目次
固定費と変動費の違い

企業の経営管理では、固定費と変動費の違いを正確に把握することは必須です。
それぞれの特徴を解説します。- 固定費とは?
- 変動費とは?
固定費とは?
固定費とは、売上や生産量の増減に関わらず一定額で発生する費用です。
人件費や地代家賃、減価償却費、リース料、保険料などが該当します。
人件費における固定費は以下のとおりです。
- 正社員の給与: 基本給や役職手当など、毎月固定で支払われる給与
- 役員報酬: 役員に対して毎月固定で支払われる報酬
- 社会保険料の会社負担分: 従業員の社会保険料のうち、会社が負担する部分
- 福利厚生費: 従業員の福利厚生のためにかかる費用(住宅手当、通勤手当など)
企業の経営では、固定費の割合が高いと売上が低迷した際の負担が大きくなりやすいため、適切な管理が求められます。
変動費とは?
変動費とは、売上や生産量に応じて増減する費用です。
原材料費や販売手数料、外注費、配送費などが挙げられます。
人件費における変動費の具体例は、以下を参考にしてください。
- アルバイト・パートの給与: 時給制で、労働時間に応じて支払われる給与
- 残業代: 所定労働時間を超えて労働した場合に支払われる割増賃金
- インセンティブ: 売上目標達成など、成果に応じて支払われる報酬
- 派遣社員の人件費: 労働時間や日数に応じて派遣会社に支払う費用
変動費は業績に応じてコストを調整しやすいです。
ただし、固定費か変動費かどうかを厳密に区別するのは難しく、多くの費用が両方の特性を持ち合わせています。
例えば、残業代や歩合給のように、労働時間や成果に応じて変動する人件費は変動費に分類されます。
一方で基本給や賞与など、成果や労働時間に関係なく一定額が支払われる人件費は固定費として扱われるのが一般的です。
業種別に見る固定費・変動費一覧

業種によって、固定費と変動費の内訳は異なります。- 製造業の場合
- 卸・小売業の場合
- 建設業の場合
それぞれの業種でどのような費用が固定費・変動費に分類されるのかを解説します。
製造業の場合
製造業の固定費は、工場の賃料や設備の減価償却費、正社員の人件費などです。
一方で変動費には原材料費や部品費、電気代の一部、外注費などが挙げられます。
製造業では生産量の増減に伴い変動費が大きく変動するため、コスト管理が欠かせません。
固定費
直接労務費、間接労務費、福利厚生費、減価償却費、賃借料、保険料、修繕料、水道光熱費、旅費、交通費、その他製造経費、販売員給料手当、通信費、支払運賃、荷造費、消耗品費、広告費、宣伝費、交際・接待費、その他販売費、役員給料手当、事務員(管理部門)・販売員給料手当、支払利息、割引料、従業員教育費、租税公課、研究開発費、その他管理費
変動費
直接材料費、買入部品費、外注費、間接材料費、その他直接経費、重油等燃料費、当期製品仕入原価、当期製品棚卸高―期末製品棚卸高、酒税
参照:中小企業庁「損益計算書の内訳の作り換え」
卸・小売業の場合
卸・小売業では、店舗の賃料や固定スタッフの人件費、広告宣伝費などが固定費に分類されます。
複数の店舗を運営する企業では、賃料負担が大きくなるため、売上とのバランスを考慮した経営が必要です。
一方で変動費には、仕入れ原価や販売手数料、配送費などが含まれます。
売上に応じて仕入れ量を調整できるため、変動費の管理がしやすい業種です。
しかし、在庫管理を適切に行わないと不要なコストが発生するリスクが高まります。
固定費
販売員給料手当、車両燃料費(卸売業の場合50%)、車両修理費(卸売業の場合50%)販売員旅費、交通費、通信費、広告宣伝費、その他販売費、役員(店主)給料手当、事務員(管理部門)給料手当、福利厚生費、減価償却費、交際・接待費、土地建物賃借料、保険料(卸売業の場合50%)、修繕費、光熱水道料、支払利息、割引料、租税公課、従業員教育費、その他管理費
変動費
売上原価、支払運賃、支払荷造費、支払保管料、車両燃料費(卸売業の場合のみ50%)、保険料(卸売業の場合のみ50%)、注:小売業の車両燃料費、車両修理費、保険料は全て固定費
参照:中小企業庁「損益計算書の内訳の作り換え」
建設業の場合
建設業では、重機や設備の減価償却費、事務所の賃料、管理職の人件費が固定費として計上されます。
一方で変動費には、材料費や外注費、工事ごとの作業員の人件費などが挙げられます。
建設業はプロジェクトごとにコスト構造が変わるため、それぞれの固定費と変動費を正確に把握し、適切な価格設定を行うことが重要です。
固定費
労務管理費、租税公課、地代家賃、保険料、現場従業員給料手当、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、交際費、補償費、その他経費、役員給料手当、退職金、修繕維持費、広告宣伝費、支払利息、割引料、減価償却費、通信交通費、動力・用水・光熱費(一般管理費のみ)、従業員教育費、その他管理費
変動費
材料費、労務費、外注費、仮設経費、動力・用水・光熱費(完成工事原価のみ)運搬費、機械等経費、設計費、兼業原価
参照:中小企業庁「損益計算書の内訳の作り換え」
人件費を変動費に変えるメリット

人件費を固定費から変動費に変えるメリットは以下のとおりです。- 経費の削減ができる
- 経営の柔軟性が向上する
- 人材活用の効率化が図れる
それぞれのメリットを解説します。
経費の削減ができる
人件費を固定費から変動費に変えると、企業は経費を効率的に削減できます。
固定費としての人件費は、売上が減少した際にも一定額を支払い続けなければならず、経営に大きな負担をかける要因です。
しかし業務委託や派遣社員の活用、成果報酬型の給与体系を導入すれば、業績に応じた支払いが可能になり、無駄なコストを削減できます。
特に繁忙期と閑散期の差が大きい業種では、必要な時期に応じて人件費を調整できるため、コストの最適化が実現します。
固定的に発生する社会保険料や福利厚生費の負担を抑えられ、結果的に全体の支出を削減できる点もメリットです。
経営の柔軟性が向上する
人件費を変動費にすれば、経営の柔軟性が向上できます。
景気の変動や市場の変化に迅速に対応するためには、人件費を一定に維持するのではなく、業績に応じて調整できる仕組みを整えることが必須です。
業務委託やフリーランスの活用、短期契約社員の採用を進めると、事業の拡大・縮小に応じた人員配置ができます。
新規事業やプロジェクト単位で専門スキルを持つ人材を確保しやすく、企業の成長を加速させるメリットもあります。
人材活用の効率化が図れる
人件費を変動費に移行すると、企業は人材活用の効率化が目指せます。
従来の固定的な雇用形態では、業務量の増減に関わらず、一定の人員を抱える必要がありました。
しかし業務委託や契約社員、派遣社員を活用すると、必要なスキルを持つ人材を適切なタイミングで確保できます。
定期的な見直しを行いながら、事業に応じた最適な人材を配置できれば、組織全体のパフォーマンスが向上します。
人件費を変動費に変えるデメリット

人件費を固定費から変動費に変えるメリットもありますが、デメリットもあります。
- 従業員のモチベーションが低下する
- 優秀な人材が流出する可能性がある
- ノウハウが蓄積されにくい
デメリットを解説します。
従業員のモチベーションが低下する
人件費を変動費に変更すると、従業員のモチベーションが低下する可能性があります。
成果報酬型や契約社員・派遣社員の活用を増やした場合、収入の安定性が失われると不安を感じる従業員も少なくありません。
雇用形態の変更により、福利厚生の対象外となるケースが増えれば、従業員の企業への帰属意識が薄れて仕事への意欲が低下します。
給与の変動が大きくなると、業務への取り組み方に影響を及ぼし、短期的な成果のみを追求する傾向が強まる可能性も高いです。
人件費を変動費化する際には、報酬制度の透明性を確保し、適切な評価基準を設けましょう。
優秀な人材が流出する可能性がある
人件費を変動費に変更するデメリットに、優秀な人材の流出リスクが高まる点も挙げられます。
固定給が減り、成果報酬や契約ベースの給与体系になると、安定した収入を求める優秀な人材が待遇の良い企業へ転職するリスクが高いです。
人材の流出を防ぐためには、適切な報酬制度の設計やキャリアパスの明確化など、従業員が長く働きたいと感じる環境を整えましょう。
ノウハウが蓄積されにくい
人件費を変動費にすると、企業内にノウハウが蓄積されにくくなります。
業務委託や短期契約の従業員が増えると、ノウハウが外部に流出しやすくなり、社内の知識共有が難しくなるかもしれません。
長期間にわたって同じ業務を担当する正社員が減少すると、社内ノウハウが十分に蓄積されず、業務の生産性が低下します。
プロジェクトごとに異なる外部人材を活用する場合、一貫性のある業務フローの維持が難しくなり、社内の業務効率が悪化する可能性が高いです。
社内ノウハウの継承を意識し、業務マニュアルの作成や知識共有の仕組みを整備しましょう。
人件費を固定費から変動費へ移行する方法
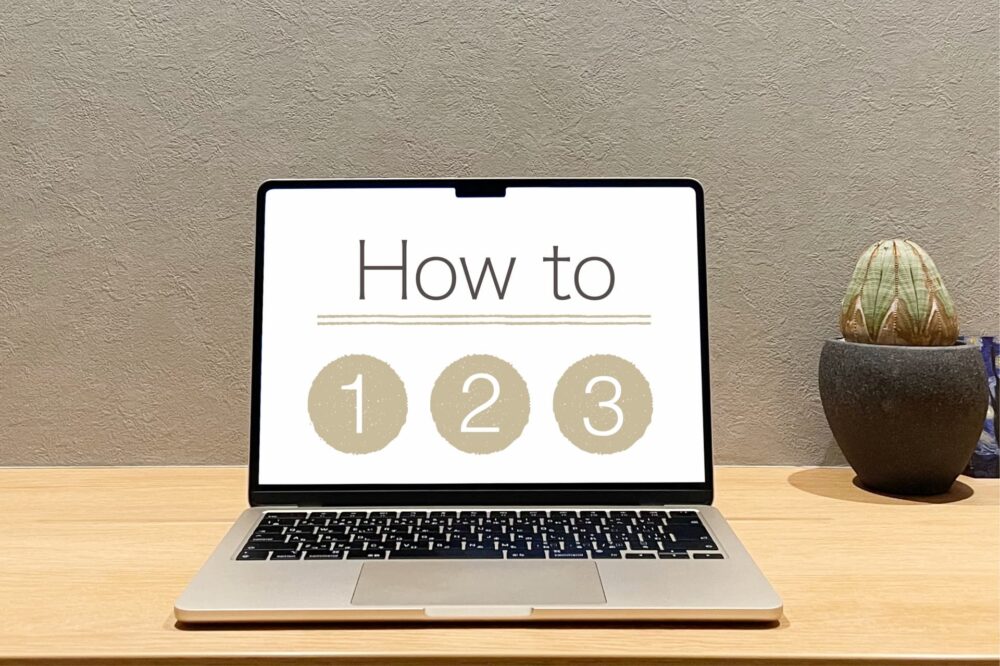
人件費を固定費から変動費へ移行するための具体的な方法は以下のとおりです。
- 成果報酬型の給与体系を導入する
- 業務委託やアウトソーシングを活用する
- 派遣社員や契約社員を採用する
それぞれの方法を解説します。
成果報酬型の給与体系を導入する
人件費を固定費から変動費に移行する方法の一つに、成果報酬型の給与体系を導入する方法があります。
従来の固定給制度では、企業の業績に関わらず一定の給与を支払う必要があり、経営が不安定な時期でも人件費の負担が変わりません。
しかし、成果報酬型の給与制度を導入すれば、社員の給与を業績に応じて変動させる仕組みが実現できます。
基本給を抑え、売上や目標達成率に応じたインセンティブを付与する仕組みを採用すると、社員のモチベーション向上に効果的です。
企業側も業績が好調時は高い報酬を支払い、不調なときはコストを抑えやすくなるため、経営の柔軟性が高まります。
ただし、給与体系を変更する際には、社員の納得を得るための説明や適切な評価制度の構築が不可欠です。
業務委託やアウトソーシングを活用する
業務委託やアウトソーシングを活用すれば、固定費である人件費を業績に応じて変動費へ移行できます。
企業内で雇用している正社員が担当していた業務の一部を、外部の専門企業やフリーランスに委託すれば、必要な時期に必要な人材を確保しやすくなります。
IT開発やマーケティング、デザイン、経理業務など専門的なスキルが求められる業務は外部の専門家に依頼すれば、高い品質を確保しつつコストの最適化が可能です。
ただし、外部に業務を委託する際は契約内容を明確にしたうえで、進捗管理や品質の維持が欠かせません。
派遣社員や契約社員を採用する
人件費を固定費から変動費へ移行するもう一つの方法に、派遣社員や契約社員の活用が挙げられます。
正社員を雇用すると、基本給や福利厚生費、退職金などのコストが継続的に発生します。
しかし、派遣社員や契約社員であれば繁忙期など必要な期間のみ雇用できるため、経営状況に応じた柔軟な人材管理が可能です。
ただし、長期的な人材の確保や企業文化への適応など正社員と比べて課題もあります。
現場の担当者と派遣社員や契約社員との円滑なコミュニケーションを心がけ、双方にとって働きやすい環境を整えましょう。
固定費と変動費から見る経営分析の指標

変動費と固定費から分析できる4つの指標は以下のとおりです。
- 限界利益
- 損益分岐点
- 安全余裕率
- 売上高変動費比率
それぞれの指標を解説します。
限界利益
限界利益とは、売上高から変動費を差し引いた金額です。
企業が固定費を回収し、最終的な利益を確保するための指標で、限界利益が高いほど売上の増加が直接利益の向上につながりやすくなります。
以下の計算式で求められます。
限界利益 = 売上高 – 変動費
限界利益率 = 限界利益 ÷ 売上高 × 100売上高が1,200,000円、変動費が720,000円の場合、限界利益は480,000円、限界利益率は40%となります。
損益分岐点
損益分岐点とは、企業の売上と費用が等しくなり、利益がゼロとなる売上高を指します。
損益分岐点を超えると、企業は利益を得られます。
損益分岐点の計算式は以下のとおりです。
損益分岐点売上高 = 固定費 ÷(1 – 変動費 ÷ 売上高)
固定費が1,000,000円、変動費率が40%の場合、損益分岐点売上高は以下のようになります。
1,000,000円 ÷(1 – 0.4) = 1,666,667円
1ヶ月に1,666,667円以上の売上を達成しない限り、利益を出せません。
損益分岐点を下げるためには、固定費を削減するか、限界利益率を高める必要があります。
安全余裕率
安全余裕率は、現在の売上高が損益分岐点をどれだけ上回っているかを示す指標です。
企業がどの程度まで売上の減少に耐えられるかを判断できます。
安全余裕率の計算式は以下のとおりです。
安全余裕率 =(売上高 – 損益分岐点売上高) ÷ 売上高 × 100
月間売上高が2,400,000円、損益分岐点売上高が2,000,000円の場合、(2,400,000円 – 2,000,000円) ÷ 2,400,000円 × 100 = 16.67%
安全余裕率は10〜20%が目安で、低すぎる場合は経営リスクが高まるため注意が必要です。
安全余裕率を改善するには、売上を増加させるか、固定費を削減して損益分岐点を引き下げる必要があります。
売上高変動費比率
売上高変動費比率は、売上高に占める変動費の割合を示す指標です。
比率が高い場合、売上の変動に対して費用も変化するため、利益の安定性が低くなる可能性があります。
一方で比率が低い場合は、売上が減少しても利益が確保しやすいです。
売上高変動費比率の計算式は以下のとおりです。
売上高変動費比率 = 変動費 ÷ 売上高 × 100
月間売上高が3,000,000円、変動費が1,200,000円の場合、1,200,000円 ÷ 3,000,000円 × 100 = 40%
業種により平均的な数値は異なりますが、70〜80%が標準です。比率が高すぎると利益の確保が難しくなるため、コスト管理を強化し、適切な価格設定を行いましょう。
固定費と変動費の分析方法

固定費が多いと売上の変動に対するリスクが高まり、変動費が多いと利益率の安定性が低下する可能性があります。
固定費と変動費のバランスを適切に分析する方法は以下のとおりです。
- 損益分岐点分析を活用する
- 変動比率を算出する
- 固定費・変動費の最適化する
- 定期的に見直す
それぞれの方法を解説します。
損益分岐点分析を活用する
損益分岐点分析は、企業が黒字になるために必要な最低売上高を把握するための手法です。
売上高が損益分岐点を上回ると利益が発生し、下回ると赤字になります。
固定費と変動費のバランスを適切に調整し、コスト削減や利益向上の戦略を立てましょう。
固定費の割合が高い企業では、損益分岐点が高くなりやすいため、固定費の削減が経営の安定化につながります。
変動比率を算出する
変動比率とは、売上高に対する変動費の割合を示す指標です。
変動比率が高い場合は、売上の増減によって利益が大きく変動しやすく、経営の安定性が低くなる可能性があります。
変動比率が低い場合は、固定費の割合が大きくなり、一定の売上が確保できれば高い収益を維持しやすいです。
企業は変動比率を分析すると、価格戦略やコスト管理を最適化し、持続可能な収益モデルを確立できます。
固定費・変動費を最適化する
経営効率を向上させるためには、固定費と変動費のバランスの最適化は欠かせません。
固定費の割合が高すぎると、売上が減少した際に大きな損失を被る可能性があるため、コスト削減が求められます。
一方で変動費の割合が高すぎると、売上が伸びた際の利益率が低くなるため、利益最大化の妨げになります。
外注や業務委託の活用、フリーランスや派遣社員の導入など柔軟な人材戦略を取り、固定費の削減と変動費の最適化を目指しましょう。
定期的に見直す
固定費と変動費の構成は、事業環境や市場動向の変化によって影響を受けるため、定期的な見直しが不可欠です。
新しい技術の導入や業務効率化によりコスト削減が見込まれるため、継続的な分析と改善が求められます。
売上の増減に応じたコスト削減や投資判断を適切に行い、企業の収益性を向上させましょう。
人件費・固定費に関するよくある質問

人件費や固定費に関するよくある質問をまとめました。
人件費削減は違法?
企業が人件費を削減する際は、労働基準法や労働契約法を守る必要があります。
従業員の給与を勝手に減額したり、不当な解雇を行ったりすることは違法です。
解雇をする場合、労働契約法第16条によると正当な理由が必要であり、業績不振を理由に解雇する際も合理的な手順を満たさなければなりません。
労働基準法第20条では、事前の予告なしに突然解雇するのも違法とされ、解雇を実施する場合は30日以上前の予告または解雇予告手当の支払いが必要です。
給与の削減についても、労働者の同意が不可欠です。
企業が一方的に給与を減額すると、労働契約法第8条の労働条件の不利益変更の禁止に違反する可能性があります。
給与体系の変更を行う際は、社会保険労務士や弁護士など専門家に相談しながら進めるのが望ましいでしょう。
固定費の人件費を下げる方法は?
固定費として計上される人件費を削減する方法は複数あります。
外注や業務委託を活用すれば、固定的な人件費を変動費に置き換える対応が可能です。
例えば、一部の業務をフリーランスや派遣社員に任せると、必要な時期に応じて人材を確保できるためコストの抑制につながります。
テレワークを推進すれば、オフィスの維持費や通勤手当の削減も期待できます。
業務プロセスを見直し、不要な作業を削減すると、人員を適正に配置しながら総人件費を抑えることが可能です。
ただし、コスト削減を優先しすぎると、従業員のモチベーション低下を招く恐れがあるため慎重に進めましょう。
人件費はどうやって計算するのか?
人件費は、給与や賞与のほか、社会保険料や福利厚生費を含めた総額で計算されます。
基本的な計算式は以下のとおりです。
人件費 = 基本給 + 賞与 + 各種手当 + 法定福利費 + 福利厚生費
法定福利費には、企業が負担する健康保険や厚生年金、雇用保険、労災保険など社会保険料が含まれます。
人件費が固定費か変動費かを適切に判断し、経営の安定と成長を目指しましょう

人件費は企業の経営において重要なコストの一つであり、固定費と変動費のどちらに分類するかによって、経営戦略の柔軟性が変わります。
人件費は固定費と考えると、安定した雇用を確保できますが、経済状況の変化に対する対応が難しいです。
一方で人件費を変動費化すれば、経営の柔軟性を高めてコスト削減につなげられます。
しかし、従業員のモチベーション低下や優秀な人材の流出といったデメリットも考慮しなければなりません。
経営の安定と競争力の向上を実現するために、適切に人件費が固定費かどうかを見極めましょう。
Fammアシスタントオンラインは、事務業務や経理サポートなどさまざまな業務に対応可能なオンラインアシスタントサービスです。
柔軟なプランとリーズナブルな料金でコスト削減を支援します。
業務効率化やコスト削減を検討中の企業は、ぜひFammアシスタントオンラインの利用を検討してください。
\ 月額¥60,000~利用できる /
資料「Fammアシスタントオンラインサービス」
を無料ダウンロード

