業務整理のメリットとコツ|整理の流れと役立つフレームワークも解説
-

-
業務整理とは、業務のムリ・ムダ・ムラを無くすために業務を可視化し、把握する作業のことです。
業務の効率化や業務改善のため、事前に業務上の課題を洗い出しておかなければ改革に着手することは困難です。
あらかじめ業務を整理しておくことで、解決すべき課題が明確化され、改革の方法と方向性が定まりやすくなります。
本記事では、業務整理で期待できる効果と具体的な方法、注意点について解説します。
業務整理に役立つフレームワークも紹介するので、業務の改善にお役立てください。
この記事でわかること
- 業務整理で見込まれる効果と実施方法
- 業務整理の注意点と役立つフレームワーク
- 整理後の業務のアウトソーシングならFammアシスタントオンラインがおすすめ
\ 月額¥60,000~利用できる /
資料「Fammアシスタントオンラインサービス」
を無料ダウンロード目次
業務整理とは

業務整理とは、社内の業務を可視化し整理することです。非効率な工程や複雑すぎる工程、ムダなタスクを見直し、業務効率の向上とコスト削減につなげます。
業務整理は現状の業務状況と優先順位を明確にできるだけでなく、業務フローやマニュアルを整理するうえでも有用です。また、事業計画の見直しや目標設計のために業務整理が行われる場合もあります。
業務整理の過程で業務フローが可視化されれば、業務が属人化している箇所やタスクの滞留などの課題を洗い出せます。
明らかになった課題に対する改善策を立て、効果測定するサイクルを繰り返すことで、中長期的な業務改善へとつなげることが可能です。
業務整理により見込まれる効果

業務整理を行うことによって組織に以下の効果が見込まれます。
- 業務品質が向上する
- 業務効率化につながる
- 従業員のモチベーションが向上する
業務品質が向上する
業務整理の記録を活用すれば業務品質の向上につながります。
業務の洗い出しをする中で、ルーティン化・定型化できる業務が見つかることは少なくありません。ルーティン化や簡潔化できる業務はマニュアル化しやすく、再現性が高まるため担当者を問わず同じ業務成果が期待できます。
また、業務整理の過程で挙がった修正箇所の改善策を業務フローに反映することで、抜け漏れやミス・遅延を削減することも可能です。業務やサービスの品質が向上すれば、顧客満足度や企業イメージの向上にもつながります。
業務効率化につながる
業務を洗い出し整理することで業務効率化につながります。
業務整理を進めることによって、非効率的なプロセスやムダな作業を発見できます。
例えば業務リソース不足を解消したい場合に、業務の洗い出しを行うと「どの業務に、どれくらいの時間を割かれているのか」を把握でき、時間やコストの削減につなげることが可能です。
また業務を整理しておけば、タスクの優先順位が明確化され業務の進捗が予測しやすくなるため、スケジューリングが容易になります。
業務が効率化され計画的に進めることで、企業の生産性が向上し競争力アップにもつながるでしょう。
従業員のモチベーションが向上する
業務整理によるフローの改善は、従業員のモチベーション向上にも効果的です。
業務が整理されることで業務とタスクの目的や意味が明確になり、成果が定義づけされるので、仕事に対する意欲が高まります。非効率な作業を手放せたことで、従業員は与えられたタスクに納得でき、仕事満足度とコミットメントも向上します。
従業員の仕事に対する意欲ややりがいが向上すれば、企業に対するエンゲージメントも向上するでしょう。
業務整理の流れ

業務整理の効果を最大化するためには、適切なステップで整理を行うことが必要です。ここでは業務整理の標準的な流れを解説します。
- タスクを洗い出しリスト化する
- 業務フロー図を作成する
- 整理できる業務や改善点を洗い出す
- 改善点と業務フローを共有する
1.タスクを洗い出しリスト化する
まず現状の業務を正確に把握するために、すべてのタスクを棚卸し(洗い出し)します。
業務を洗い出してリスト化する際には、タスクの内容と担当者を記載することがポイントです。洗い出した業務の内容は作業ベースで細分化しましょう。
タスクを細分化しておくことで作業に必要な時間を見積もりやすく、業務スケジュールが立てやすくなります。
さらに、目の前の業務だけでなく関連する前後の業務にも目を向けることで、抜け漏れなくタスクを洗い出すことが可能です。
すべての担当者とタスクを可視化しリスト化することで、誰にどの作業を割り当てればよいかを明確にできます。
2.業務フロー図を作成する
タスクを洗い出しリスト化できたら既存業務のフロー図を作成します。
業務フロー図とは業務フロー全体を把握するために、業務ごとの工程や流れ、関わるメンバーや場所、機材にいたるまでを図形や矢印で図式化したものです。
まずタスクの処理プロセスについて、メンバーを横に、時系列を縦に並べて整理します。次に、各タスクの前後の関係性を明確にします。
「前のタスクが完了しないと着手できない」「前のタスクの完了を待たずに着手できる」タスクに分け、前後の関係性を明確化します。
最後にタスク同士の関係性や条件分岐などを、矢印でマインドマップ状に書き込めば完成です。
現状のフロー図を作成する過程で、新たな課題や疑問が挙がってくることも少なくありません。現状のフローを客観視することで、不要な作業や適切でない流れを発見でき、改善策や効率化のアイディアが生まれやすくなります。
3.整理できる業務や改善点を洗い出す
可視化された業務フロー図を関係部署やスタッフで分析し、改善点を洗い出します。
そして洗い出したひとつひとつの改善点に対し、以下の流れで根本的な改善策を検討しましょう。
- 廃止・削減できる業務はないか
- もっとやりやすい方法はないか
- ルール化・マニュアル化できないか
- 計画化できないか
- スキルや経験に見合った負荷や分担になっているか
- まとめてできるタスクはないか
- 機械化・自動化できないか
業務を多角的に見直すことで、他部署やアウトソーシングに移管できる業務も見つけられるでしょう。改善策の立案時には、他の業務に影響を及ぼす可能性も考慮し、前後の工程に関わる部署とも協議のうえ検討しましょう。
4.改善点と業務フローを共有する
改善点が明確になったら業務フローを再設計し、関係者に共有します。
挙がった改善策に対し、効果やコスト、関係者への影響などの視点から、実現の可能性が高く効果的なものから優先的に実施することが大切です。
改善案の数が多く、どれを優先してよいか判断できない場合は「現状の業務負担の大きさ」と「全体で見込める効率化効果の程度」を基準に優先度を決めることをおすすめします。
続いて改善策を実行する期限とスケジュールを立案し、すべての関係者に共有します。スケジュールに必要なリソースと担当者、費用も組み入れておくことで、改善策を円滑に進めることができます。
業務整理のルール
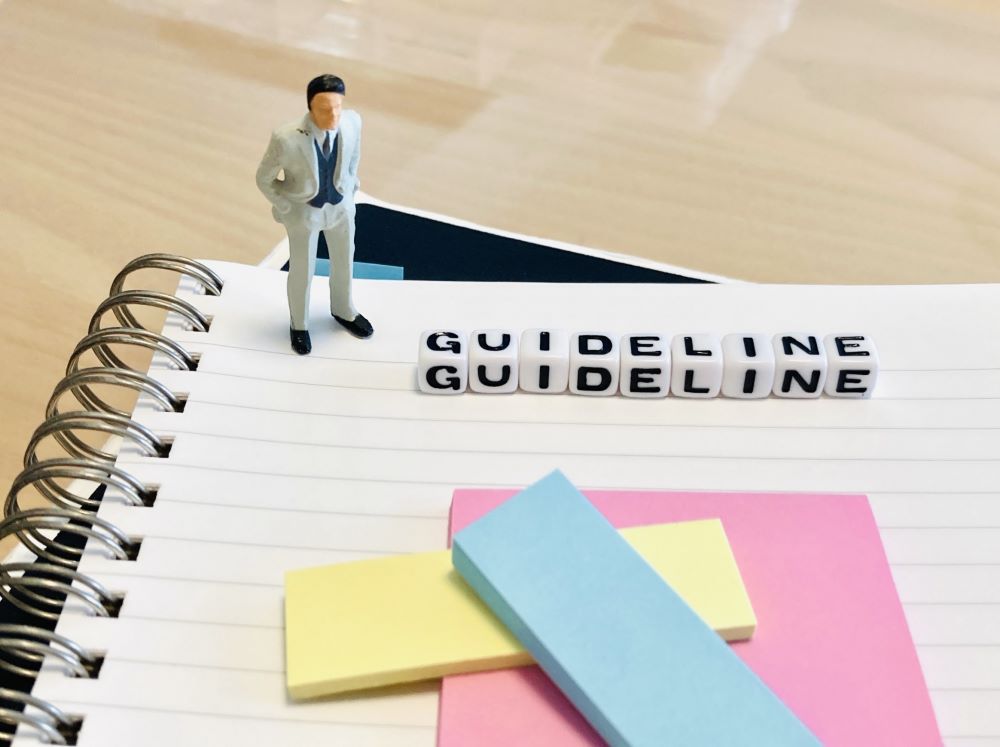
業務整理を行っても、情報が活用されなければ意味がありません。業務整理の効果を最大化するために守るべきルールは以下のとおりです。
- 業務の順番がわかるよう記録する
- 誰が見てもわかる内容にまとめる
- 情報の置き場を一カ所に統一する
フロー図やマニュアル、業務一覧表などの業務情報をツールに記録する際には、関係者の誰が見ても同じ作業をイメージできるよう記載されている必要があります。
整理した業務内容や改善策が共通認識として定着するためにも、アイコンや矢印の引き方などの記載ルールは統一しましょう。
また、実務担当者や新入社員、異動者などの業務未経験者でも理解できるよう、平易な表現で記載することも大切です。
そして紙ベース・データベースどちらであっても業務情報の置き場所は一カ所にまとめ、見つけやすい形式でいつでも参照できる状態にすることも重要です。
業務を整理するうえで注意すべきポイント

業務の改善効果を高めるために、業務整理で注意すべきポイントは以下のとおりです。
- 時間をかけて業務を細かく洗い出す
- 関係者の意見をヒアリングしながら整理する
- 必要な業務まで削減しない
- PDCAサイクルを回し改善する
時間をかけて業務を細かく洗い出す
業務を可視化するためには、業務の洗い出し時にできるだけ粒度を細かく分解することが不可欠です。
業務の分解が不十分な場合、業務整理の精度が低く必要な作業情報が不足するため、未経験者が業務を行えるほどの詳細な標準化には至りません。
結果として業務を行えるのは習熟した担当者のみに限定され、属人化を招く恐れがあります。
粒度の細かい洗い出しには2~3カ月以上の時間がかかることが一般的です。余裕を持ったスケジュールで業務の洗い出しに着手し、施策が見切り発車にならないよう留意しましょう。
また、定期的に発生する業務は無意識で処理しがちなため、時系列で回想したり、年間スケジュールを再度確認したりすることで、洗い出しの抜け漏れを防ぐことも大切です。
関係者の意見をヒアリングしながら整理する
業務の洗い出しの精度を高めるためには、実務担当者や関係者へのヒアリングが不可欠です。
実務担当者へ業務のヒアリングを行うことで、業務を細かい粒度で分解し分析できます。また、現場の実務担当者と管理者だけでなく取引先などの意見を取り入れることで、多面的に業務を見直すことが可能です。
社内関係者へのヒアリングは以下の方法を組み合わせて実施することで、より正確な情報を収集できます。
- 現場での立ち会い調査
- 意見箱の設置
- 業務調査票の配布やインタビューの実施
- 業務洗い出しのミーティングやワークショップの開催
記入方式のみで業務を洗い出すと、記載者ごとのレベル感や粒度が異なるため、情報に差異が生まれることもあるでしょう。そのため、現場に立ち会い直接確認することも必要です。
関係者の意見を多く採用することで、改善策への協力も得やすくなるでしょう。
必要な業務まで削減しない
業務を整理する際には、必要な業務まで削減しないよう注意しましょう。
ムダな業務を削減できれば、重要な業務により多くのリソースを投入できます。しかし業務のスリム化を急ぐあまりに削ってはいけない作業を削ってしまうと、却って業務のフロー全体の効率が低下してしまう恐れがあります。
以下のポイントで必要な業務と不要な業務を見分けることが大切です。
- 業務に明確な目的があるか
- 取引先や顧客に価値を提供できるか
- 将来の事業計画との整合性があるか
現場の作業スピードが向上するとしても、顧客に価値を提供する仕事を削減するのは本末転倒です。逆に一見ムダに見えても、その業務によって将来の成果が見込まれる場合は削減すべきではないでしょう。
仮に判断を誤った場合でも切り替えが利くように、大規模な業務削減は少しずつ段階的に進めていく方が安心です。
PDCAサイクルを回し改善する
改善策は一回で成功しようと思わず、PDCAサイクルを回し改善し続けることが大切です。
業務整理を始めるにあたり、何から着手して良いかわからずゴーサインを出せないこともあるかもしれません。しかし業務の可視化を進めるうちに進め方が見えてくるため、まずは成否にこだわらず実行してみることが大切です。
また、業務を取り巻く環境は刻々と変化するため、常に最新の業務状況に合わせたアップデートが必要です。数カ月・半年ごとの定期的な見直しで業務リストを更新し、改善をサイクル化しましょう。
業務整理に役立つ6つのフレームワーク

最後に、効果的な業務整理に役立つフレームワークを6つ紹介します。
- MECE(ミーシー)
- ECRS(イクルス)
- BPMN
- ロジックツリー
- QCD
- KPT
MECE(ミーシー)
MECE(ミーシー)は以下4語の頭文字を取った単語で「漏れなく重複もない」を表します。
- Mutually(相互に)
- Exclusive(重複せず)
- Collectively(全体として)
- Exhaustive(漏れがない)
MECEは問題をロジカルシンキングで解決するための原則的なフレームワークです。課題の答えを導き出す際に、複雑な問題をシンプルに切り分けることによって、原因解明や解決の道筋を立てやすくなります。
なお、MECEは業務を可視化し整理する際の基本原則ではあるものの、前提条件が誤っている場合は誤りを含んだまま進行してしまうため、前提条件の精査が必要です。
ECRS(イクルス)
ECRS(イクルス)は以下4つの原則の頭文字を取った言葉で、改善が必要な箇所を抽出するためのフレームワークです。
- Eliminate(排除:必要性を見極める)
- Combine(結合:類似する業務をまとめる)
- Rearrange(交換・再配置:プロセスの見直しを行う)
- Simplify(簡素化:誰でもできるようにする)
ECRSでは1~4の順に検証を行います。まずムダな業務を排除、または同期化できる工程を洗い出し、次に工程の再配置で効率化できないか、もっと簡素化できないか改善策を検討するという流れです。
ECRSはコスト削減や属人化の解消、ヒューマンエラーの防止、生産性の向上に効果を発揮するフレームワークで、業種を問わず活用できます。
BPMN
BPMNは業務フローの表記方法の一つで、以下の4つの頭文字を取った言葉です。
- Business(仕事)
- Process(過程)
- Model(モデル)
- Notation(表記)
BPMNでは記号や図形(丸や四角など)を使って業務フローを階層的にモデリングします。
表記の手順は、業務全体を俯瞰してゴールや目的を設定し、詳細な業務情報を棚卸ししたら、業務の詳細項目を入れて設計する流れです。
表記法は「実線=作業の流れ」「破線=外部との連携」「点線=書類やデータの流れ」に統一され、世界標準化されています。
社内のフロー表記をBPMNで統一することで、部署間での認識共有がしやすくなるでしょう。ただし表記の際は時系列を意識し、記号や矢印が複雑になりすぎないよう注意が必要です。
ロジックツリー
ロジックツリーとは、特定の物事や問題を論理的に分解し、階層化して整理するためのフレームワークです。
ロジカルシンキングの一手法で、物事に含まれる要素を以下のように分解し、階層化していきます。
- Whyツリー(原因研究)
- Whatツリー(要素分解)
- Howツリー(問題解決)
事象をマインドマップのようにツリー化して分析することで、効率的な問題解決や意思決定ができることも特徴です。
例えばWhyツリーの場合、特定の課題に対して、原因を導き出し、さらにその原因を深掘りすることで、問題の根本的な要因を見出せます。
同様にHowツリーで同じ課題に対する改善案を洗い出し、Whatツリーで特定の箇所や工程を可視化することが可能です。
ロジックツリーを用いれば問題の全体像を把握しながら、問題の解決策を論理的に深掘りできます。
QCD
QCDとは、以下の3つの頭文字を取った造語で、製造業やシステム開発などの物づくりに重要な項目をまとめたものです。
- Quality(品質)
- Cost(コスト)
- Delivery(納期)
上記の3つは一見相反関係にあり、いずれかを立てれば他を立てることが難しい要素です。例えば品質を重視すればコストが嵩みやすく、納期と顧客満足度を優先すれば、社内の製造現場に多大な負担がかかります。
物づくりの現場においては、3つのバランスを意識しながら状況に応じて優先順位を決め、業務を進めることが大切です。
実際にはQuality(品質)を最優先することが大前提で、Cost(コスト)とDelivery(納期)は顧客と現場の状況により適宜判断することが適切といえます。
KPT(ケーピーティー・ケプト)
KPT法とは、チームで以下について議論する振り返りのフレームワークのことです。
- Keep=よかったこと(成果が出ていて継続すること)
- Problem=直したいこと、悪かったこと(解決すべき課題)
- Try=どう改善するのか(次に取り組むこと)
KPT法はもともとシステムのアジャイル開発の振り返りに使用されているフレームワークですが、現在では幅広い業態で応用されています。
ホワイトボードと付箋、もしくはスプレッドシートなどを使って手軽に意見を出し合えることがメリットです。
KPT法には課題の早期検出と解決、コミュニケーション促進によるナレッジ共有や組織力強化、継続的な改善スパイラルを構築できるなどの利点もあります。
実施タイミングは毎週・毎月など定期的に行うか、プロジェクトの区切りがついた時点で1時間程度行うことがおすすめです。
業務整理で業務を改善し生産性を高めよう

業務整理とは業務の効率化や業務改善を前提に、現行の業務を洗い出し可視化することです。業務整理を進めることで業務品質の向上だけでなく、従業員の働きやすさにもつながります。
業務を整理する際には業務を細分化して洗い出すことと、整理した情報を誰でも活用しやすい方法で保管することが大切です。
業務整理を業務改善につなげるためには、一時的な業務負荷の変動に対応できるリソースが必要です。例えば業務整理で洗い出した定型業務をアウトソーシングすることで、自社従業員が業務改革に専念できます。
Fammアシスタントオンラインなら必要な業務を必要な時間だけ委託することが可能です。業務整理で自社の生産性向上に弾みを付けたい方はぜひご相談ください。
\ 月額¥60,000~利用できる /
資料「Fammアシスタントオンラインサービス」
を無料ダウンロード

